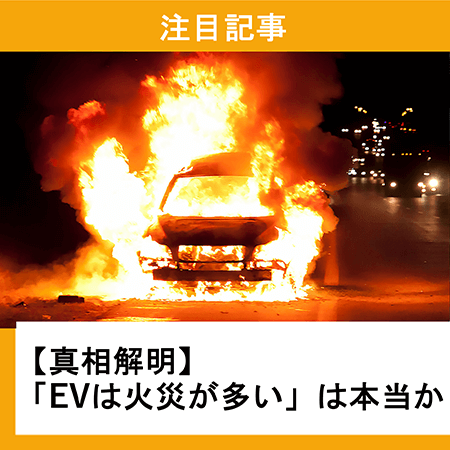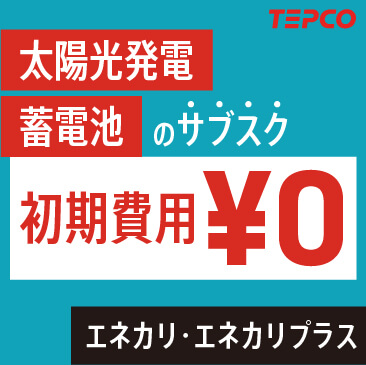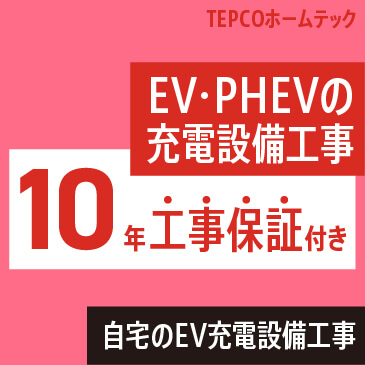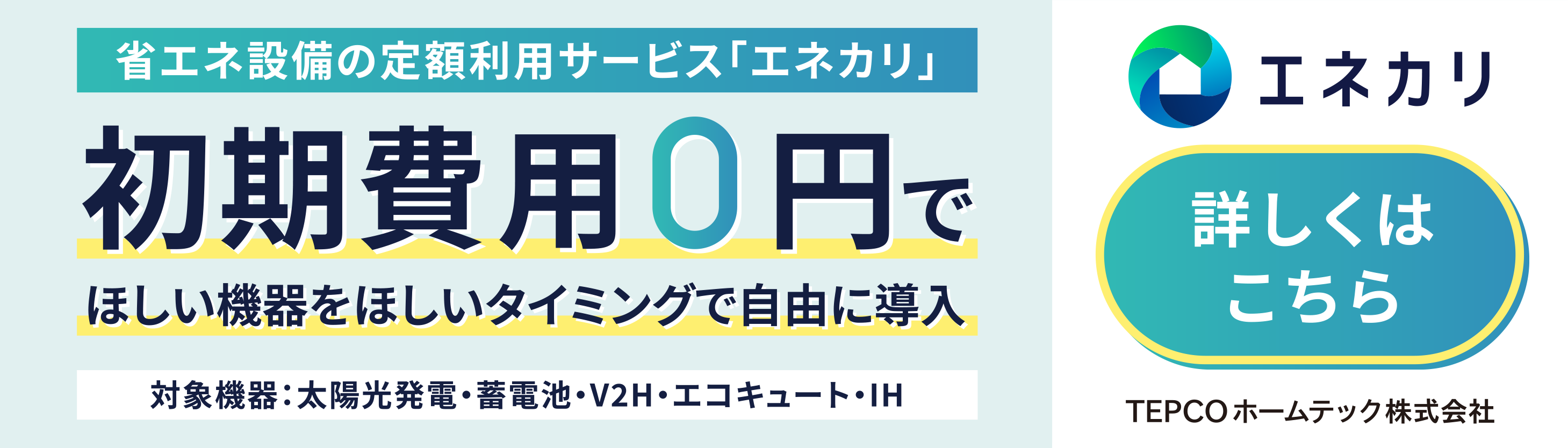「V2H」は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の大容量バッテリーを、自宅の電源として活用できるシステムです。この記事ではV2Hの導入費用を徹底的に解説。V2H機器を購入・リースする場合の費用相場のほか、機器の価格や工事費用、補助金や導入手順についてもご紹介します。
※この記事は2023年9月19日に公開した内容をアップデートしています。
- V2Hの設置費用の相場はいくら? 導入方法別で紹介
- V2H導入に必要なアイテムの費用は?
- V2Hの補助金はいくら出る?
- V2Hを導入するための4ステップ
- ️V2H機器を選ぶときのポイントは?
- V2Hの設置費用はそれなりに高額。補助金や定額利用サービスを上手に活用しよう
V2Hの設置費用の相場はいくら? 導入方法別で紹介

V2Hは「EVのバッテリーを家庭で有効活用するシステム」
まずはV2H(Vehicle to Home)の基本についておさらいしましょう。V2Hとは、EVやPHEVの大容量バッテリーを、家庭で有効活用するためのシステムや考え方を指す言葉です。
具体的には、専用のV2H機器を介して、EVと家の電気を行き来させたり、EVやPHEVの大容量バッテリーに電気を蓄えておいたりできるようになります。これにより、家庭で電気を効率的に使うことができるようになります。
V2Hのメリットは、主に4つあります。導入時には必ずチェックしておきましょう。
〈図〉V2Hのメリット

以下の記事ではV2Hのメリットの詳細のほか、蓄電池との違いも解説しています。併せて参考にしてください。
V2H導入方法には「購入」と「リース」がある
V2Hを導入する方法は「購入」が一般的といえるでしょう。しかし、機器代とは別で工事費もかかり、初期費用がそれなりの金額になるため、初期費用なしで月額利用料を支払う「リース」を選択することもできます。
V2H機器を購入する場合とリースを利用する場合、それぞれの設置費用の相場をチェックしていきましょう。
V2Hを購入する場合の費用相場
V2H機器を購入する場合、費用の合計は85万〜180万円程度と大きく幅が出てきます。
これはV2H機器の価格がモデルによって55万〜140万円程度と幅があり、設置工事にかかる費用は30〜40万円程度になるケースが多いためです。ただし、設置工事は家や駐車場の状況、設置する機種や配線の長さ、さらに太陽光発電の有無によって左右されます。
具体例として、もっとも一般的なV2H機器であるニチコンの「EVパワー・ステーション」と設置工事の合計金額の一例をご紹介します。
〈表〉V2Hを購入する場合の費用の一例(2024年2月時点)1、2)
| スタンダードモデル (VCG-663CN3) |
プレミアムモデル (VCG-666CN7) |
新型モデル (VSG3-666CN7) |
|
| 本体価格 | 54万7800円(税込) |
98万7800円(税込) |
140万8000円(税込) |
|---|---|---|---|
| 工事費 | 約30万~40万円(税込) | ||
| 総額 | 約85万〜95万円(税込) | 約130万〜140万円(税込) | 約170万〜180万円(税込) |
なお、V2Hは電気工事を必要とする専門機器であるため、自分で購入したり、取り付けたりすることはできません。施工業者に依頼することになります(詳しくは「V2Hの導入ステップ」参照)。️
また、一括購入時には、国や自治体の補助金を上手に利用するのもポイントで、自己負担額を大きく減らせる可能性があります️(詳しくは「V2Hの補助金はいくら出る?」参照)。
東京電力グループのTEPCOホームテックでは、V2Hの設置工事はもちろん、必要に応じ電気契約容量の変更提案、補助金の申請などもワンストップで行うことができます。
V2Hをリースする場合の費用相場
V2Hを導入する際に、機器購入のほかにリース方式で定額利用するという選択肢もあります。
たとえば、東京電力グループのTEPCOホームテックでは購入のほかに定額利用サービス「エネカリ」も提供しています。「エネカリ」を利用すれば、工事費を含む導入の初期費用が0円になるので、手軽にV2Hを導入することができます。
〈表〉「エネカリ」月額利用料(参考金額)
| プレミアムモデル (VCG-666CN7) |
|
| 利用料※ | 月額1万4300円(税込)~ |
|---|
※契約期間10年の場合。2024年2月時点の利用料金。
10年間の利用料と比べると、V2H機器を購入したほうが安価になりますが、購入の場合は自然災害による故障時やメーカー保証期間後などに自己負担リスクがあるのに対し、エネカリなら契約期間中ずっと機器保証・工事保証・自然災害補償がついているというメリットがあります。
V2Hを導入する際には、購入とリース両方のメリット・デメリットを比較したうえで、目的にあった選択をするとよいでしょう。
V2H導入に必要なアイテムの費用は?
V2Hを導入するためには「V2H機器」と「V2Hに対応するEVまたはPHEV」が必要になります。また、「太陽光発電」があるとよりV2Hのメリットを享受でき、「蓄電池」があると災害時にさらに安定した電源を確保できるようになります。️
ここでは必要なアイテムのほか、太陽光発電・蓄電池に関する費用もご紹介します。
Ⅰ.V2H機器・設置工事の費用

前述のとおり、V2H機器の価格は55万〜140万円程度です。販売メーカーによって多少の価格の違いはありますが、メーカーが限られることもあり、一般家庭用ならこの価格内で収まるでしょう。
代表的なV2H機器の価格は以下のとおりです。
〈表〉主なV2H機器の価格一覧
| メーカー名 | 製品・モデル名 | 本体価格 |
| ニチコン | EVパワー・ステーション(スタンダードモデル) | 54万7800円(税込) |
| EVパワー・ステーション(プレミアムモデル) | 98万7800円(税込) | |
| EVパワー・ステーション(新型モデル) | 140万8000円(税込) | |
| デンソー | V2H-充放電器 | オープン価格 |
| 東光高岳 | SmanecoV2H | オープン価格 |
【あわせて読みたい記事】
▶「V2H」主要メーカー3社の機器を紹介!選び方や効率的な使い方についても解説
また、機器の料金に加えて約30〜40万円の設置工事費用がかかります(駐車場が隣接している戸建住宅の場合)。
駐車場が自宅から離れていてV2H機器と自宅とを接続するケーブルの長さが余分に必要な場合や、住宅の壁面に施工が必要な場合などは追加の費用がかかるため、まずは施工業者に見積もりを依頼してみましょう(後述の「V2Hの導入ステップ」参照)。
なお、V2Hの設置工事の現場レポートを下記の記事でご紹介しています。1日がかりで行う専門的な作業ですから、これを読むと設置工事費用はある程度必要であることがわかります。
【あわせて読みたい記事】
▶【V2Hの設置現場レポート】電気のプロによる施工現場に密着!
Ⅱ.V2Hに対応するEV・PHEVの費用

V2Hを導入する場合、EVやPHEVなどの電動車ももちろん必要です。現在のところ、すべてのEVやPHEVがV2Hに対応しているわけではなく、V2H機器の機種によって対応する車種も異なります。
EVの価格相場は軽自動車だと250万円〜、普通車は300万円台後半〜となっています。
2024年2月現在でV2Hに対応している主なEV・PHEVの価格は以下のとおりです。
〈表〉V2Hに対応する主なEV・PHEVの価格 ※メーカー50音順
| メーカー名 | EV or PHEV | 車種名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| スバル | EV | ソルテラ | 627万円~ |
| トヨタ | EV | bZ4X | 550万円~ |
| 日産 | EV | サクラ | 254万8700円~ |
| 日産 | EV | リーフ | 408万1000円~ |
| 日産 | EV | アリア | 539万円~ |
| ヒョンデ | EV | KONA | 399万3000円~ |
| BYD | EV | DOLPHIN | 363万円~ |
| マツダ | EV | MX-30 EV MODEL | 451万円~ |
| マツダ | PHEV | CX-60 PHEV | 609万9500円~ |
| 三菱 | EV | eKクロスEV | 254万6500円~ |
| 三菱 | PHEV | アウトランダーPHEV | 499万5100円~ |
| メルセデス・ベンツ | EV | EQS | 1563万円~ |
| メルセデス・ベンツ | PHEV | C 350 e | 995万円~ |
| レクサク | EV | RZ | 820万円~ |
なお、EVやPHEVも補助金を利用することができ、2023年度の国のCEV補助金ではEVで最大85万円、PHEVは最大55万円が準備されていました。
V2H対応車種やEVの価格相場、補助金については、以下の記事をご参照ください。
Ⅲ.太陽光発電の費用

V2H導入の必須条件ではありませんが、V2Hのメリットをフル活用するためには、太陽光発電との連携が推奨されています。太陽光発電で作られた電気を利用することで、電気代の節約やカーボンニュートラルへの貢献が期待できるほか、災害対策を強化することもできます。
逆に言うと、すでに太陽光発電を利用している家庭は、V2Hの導入がおすすめです。また、V2Hの導入をきっかけに太陽光発電の設置を検討してもよいでしょう。
住宅用の太陽光発電を導入する場合、設置費用は85万円(3kW)~142万円(5kW)程度です(太陽光パネルのほか、パワーコンディショナ・工事費等を含む。2023年設置の既築住宅における平均費用から算出3))。
もちろん、これは目安であり、メーカーや住宅の条件によって費用は異なりますが、選択肢としては初期費用をかけずに導入する方法もあります。詳しくは、以下をご覧ください。
【あわせて読みたい記事】
▶太陽光発電の設置費用の相場は?機器の価格や売電収入との関係についても解説
初期費用をかけずに太陽光発電を導入する方法
太陽光発電を自宅に導入したいけれど、初期費用はかけたくない。そのような場合は、東京電力グループが提供しているサービス「エネカリ/エネカリプラス」がおすすめです。初期費用ゼロ円※で自宅に太陽光発電を導入できるうえ、設置からメンテナンス、保証もつくため、維持コストも含めて将来の家計を計画的に設計することができます。
「エネカリ/エネカリプラス」について詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
※「エネカリプラス」は別途足場代等の費用がかかる場合があります。
Ⅳ.蓄電池の費用

V2Hを導入される方の中には、蓄電池もセットで導入される方もいます。併用するメリットは「非常時に安定した電源を確保できること」「電気代の節約効果をより期待できること」が挙げられます。
V2HはEVやPHEVの大容量バッテリーを活用するため、それらが自宅に駐車していないと蓄電池としての機能を果たすことができません。一方で、蓄電池は自宅に固定されているため、常に緊急時などに備えることができるので、家庭用バックアップとして蓄電池を導入するケースがあるのです。
ただし、現状では蓄電池の価格はあまり安くはありません。工事費を含んだ家庭用蓄電池の目安価格は1kWhで平均13.9万円です(2022年度時点)4)。蓄電池は3kWh以上を設置するのが一般的ですから、50万円程度〜と考えておきましょう。
【あわせて読みたい記事】
▶家庭用蓄電池とは?仕組みや種類、設置するメリット・デメリットを解説
V2Hの補助金はいくら出る?
ここまでご紹介したとおり、V2H導入にはそれなりにお金がかかります。しかし、V2Hは災害時のレジリエンス(対応力)向上やカーボンニュートラルに貢献できるシステムであることから、一定の条件の下、国や自治体からそれぞれ補助金が交付されています。次の情報を確認した上で、申請を検討しましょう。
Ⅰ.国の補助金:最大115万円(2023年度)
2023年度の国によるV2H補助金(V2H充放電設備の導入補助事業)の上限額は機器購入費と工事費をあわせて115万円となっていました5)。
上記で示したとおり、V2Hの機器と設置工事の合計費用の目安は85万〜180万円程度ですから、補助金で自己負担をかなり減らすこともできるでしょう。
〈表〉補助金の上限額(2023年度の場合)
| 項目 | 金額 |
| V2H機器の購入費 | 上限75万円(補助率1/2) |
|---|---|
| 設置工事費 | 上限40万円 |
ただし、2023年度の補助金は予算上限に達し、2023年6月時点で終了しています。2024年4月から2024年度分の補助金がスタートしますので、見逃さないようにしましょう。
なお、2023年度の補助金情報や、2024年度分の最新情報は以下の記事で順次更新していきます。
【あわせて読みたい記事】
▶V2Hの補助金は上限いくら? 国や自治体の制度、注意点を解説
Ⅱ.地方自治体の補助金
また、自治体で独自の補助金を交付している場合もあります。場合によっては国のV2H補助金と併用できることもあるので、こちらもぜひ活用しましょう。
たとえば東京都の場合は、V2H導入の補助金として上限50万~100万円の交付が受けられます6)。ただし、こちらも国の補助金と同様に交付の条件があるので、ご注意ください。
補助金の申請と聞くと難しいイメージがあると思いますが、設置を請け負う施工業者がサポートしてくれるケースが多いので、導入の際に相談してみるとよいでしょう。
参考資料
5)次世代自動車振興センター「令和4年度補正・令和5年度補助金(V2H充放電設備)のご案内」
6)クール・ネット東京「【令和5年度】戸建住宅におけるV2H普及促進事業災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」
V2Hを導入するための4ステップ
V2Hを購入する場合でもリースする場合でも、V2Hを導入する際のステップは大きく変わりません。
V2H機器を自宅に設置し利用するまでの手順は、以下のとおりです。
〈図〉見積り依頼から設置までの流れ

(ステップ1)施工業者に依頼し、V2H機器を決定
V2H機器は特殊な機器ですから、一般には販売されていません。また、設置に際し電力会社などへの申請が必要です。そのため、設置には施工業者(リースのサービス事業者)に依頼を行い、まずは機器の種類を決めます。
(ステップ2)施工業者による現場調査・見積もり
施工業者(リースのサービス事業者)が現場(自宅)を訪問し、工事費用の見積もりを行います。その際の打ち合わせで、V2H機器の設置場所や配線の経路などがおおまかに決まります。
(ステップ3)工事契約(各種の申請)
現場調査が完了し工事の契約が結ばれると、V2H機器を家庭で使用するための電力申請を行います。申請は、施工業者側で代行してくれます。電力系統に連系するための電力申請や、太陽光発電のFIT制度を適用している場合の事業計画変更申請が必要になります。
〈表〉各種申請
| 太陽光発電が設置されていない住宅 | 太陽光発電が設置されている住宅 | |
| 必要な申請 | 電力申請 |
電力申請 |
(ステップ4)設置工事/配線・結線の電気工事
機器の設置は、基本的に各種の申請が完了した後で実施されます。工事が完了すれば、V2Hを利用することができます。
【あわせてチェックしたい】「V2Hシステムの設置」に興味がある方へ
▶︎EVの大容量バッテリーを蓄電装置として利用「V2Hシステム」
️V2H機器を選ぶときのポイントは?
V2H機器は製品によって性能や価格が異なります。製品のスペック表を見る際には、以下をチェックしましょう。
〈図〉V2H機器を選ぶポイント

それぞれ専門用語が使われているので理解しにくいかと思いますが、つまりはV2Hをどのように使いたいかを踏まえて選んでいきます。
たとえば、停電時に家全体まで通電させたいか、どのくらいの電気の出力を求めるかといった点のほか、V2Hは付加機能としてEVの充電速度を通常より速くできる場合もあるため、これらを選択していきます。
もちろん、使い勝手のよい機器はそれなりに値段が高くなる傾向にあるので、その点は理解しましょう。
主要な3メーカーの機器の特徴と、V2H機器の選び方については以下の記事でご紹介しています。具体的な製品例も紹介していますので、チェックしてみてください。
【あわせて読みたい記事】
▶「V2H」主要メーカー3社の機器を紹介!選び方や効率的な使い方についても解説
V2Hの設置費用はそれなりに高額。補助金や定額利用サービスを上手に活用しよう
近年V2Hは災害対策や再エネ普及の観点から大きく注目されています。ただ、普及が始まって間もないことや機器の特殊性から、それなりに高額な設備であることは否めません。
しかし、国や自治体の補助金で自己負担を減らすことができるほか、初期費用0円の定額利用サービスもあります。V2HはこれからEV・PHEVの普及とともにますます存在感が増していくことが予想されますので、ぜひ検討してみてください。
【おすすめ情報】V2H・蓄電池の導入を手軽にする「エネカリ」
東京電力グループのTEPCOホームテックでは、V2H・蓄電池の設置工事はもちろん、必要に応じ電気契約容量の変更提案、補助金の申請などもワンストップで行うことができます。
同社では、導入方法も選ぶことができ、一括購入のほか、初期費用0円で導入することができる「エネカリ」というサービスもあります。エネカリでは月額定額支払いにできるため、まとまった費用のお支払いに不安がある場合にはぜひご相談ください。