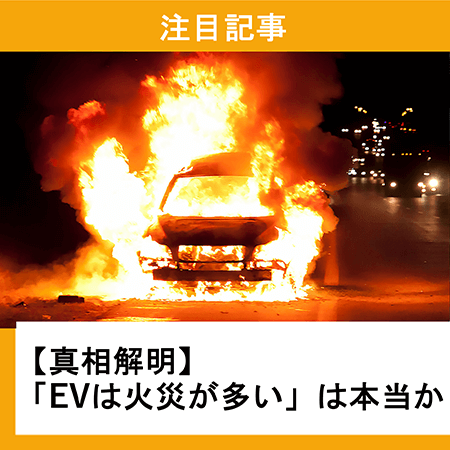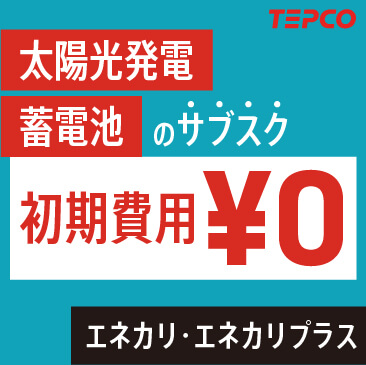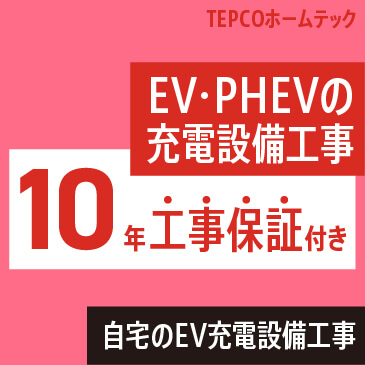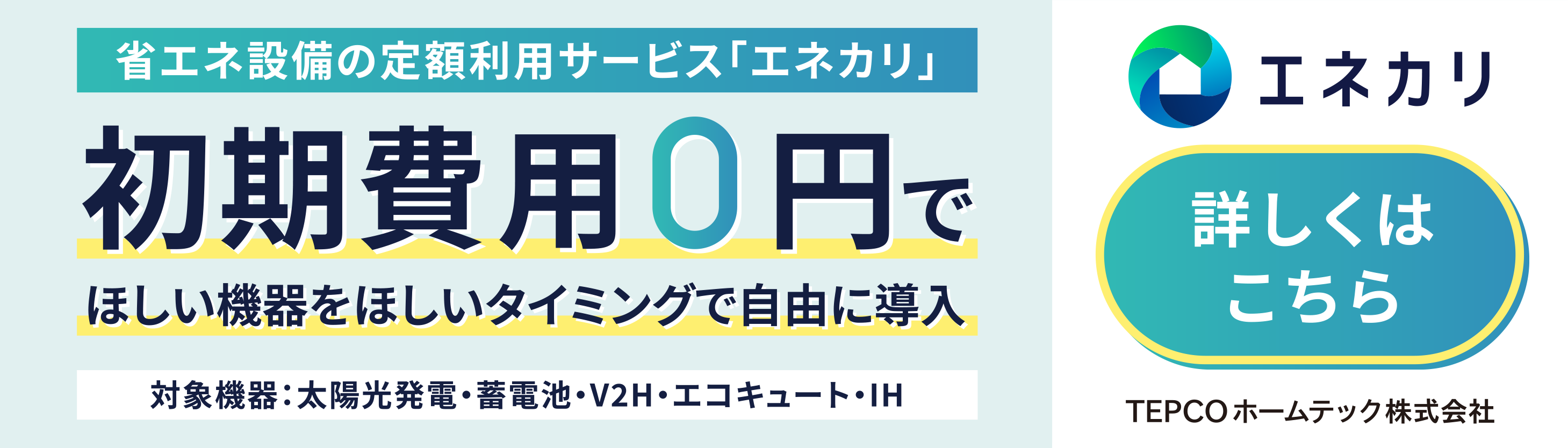大容量バッテリーを搭載する電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)は、V2Hシステムを住宅に導入することで、家庭用蓄電池としても活用することができます。災害時の備えや電気代の節約にも役立つEVやPHEVの活用方法について説明します。
- 電気自動車を家庭用蓄電池として使用する方法とは?
- 蓄電池化するのに適した電気自動車とは?
- 【比較検討】V2H機器を選ぶ基準は?
- コスパは? 電気自動車を蓄電池化するのにかかる費用
- 電気自動車×V2H×太陽光発電を併用するメリットとは?
電気自動車を家庭用蓄電池として使用する方法とは?

EVやPHEVを家庭用蓄電池として活用したい場合、V2Hシステムを導入する必要があります。V2Hとは「Vehicle to Home(車から家へ)」の略称です。EVやPHEVの大容量バッテリーに蓄えられた電気は乾電池などと同じ「直流」ですが、家庭用の電気は「交流」です。
〈図〉V2Hの主な役割

そのため、EVやPHEVを家庭用蓄電池として使用するには、「直流から交流」「交流から直流」に変換するV2H機器をEVやPHEVと住宅の間に設置する必要があります。
また、必須条件ではありませんが、V2Hの利点を最大限活用するには、太陽光発電との連携を推奨します。さらなる電気代の節約に加え、カーボンニュートラルへの貢献も期待できるからです。
蓄電池化するのに適した電気自動車とは?

V2H対応車種であることが必要
現在、すべてのEVやPHEVがV2Hに対応しているわけではない点に注意しましょう。たとえば、一部の例外を除いて、ほとんどの輸入車はV2H非対応となっています。また、V2H機器の機種によって、接続できる車種が異なる点にも気をつける必要があります。
〈表〉V2Hに対応するEV例
| メーカー | 対応車種 |
| スバル | ソルテラ |
| トヨタ | bZ4X |
| 日産 | アリア、サクラ、リーフ、e-NV200 |
| ヒョンデ | IONIQ 5 |
| BYD | ATTO 3 |
| ホンダ | Honda e |
| マツダ | MX-30 EV MODEL |
| 三菱 | eKクロスEV、i-MiEV、MINICAB-MiEV TRUCK、MINICAB-MiEV VAN |
| メルセデス・ベンツ | EQS、EQE |
〈表〉V2Hに対応するPHEV例
| メーカー | 対応車種 |
| トヨタ | プリウスPHV |
| 三菱 | アウトランダーPHEV、エクリプス クロスPHEV |
※ニチコン(EVパワー・ステーション)対応車種の場合
なお、V2H対応車種については、以下の記事で詳しく解説しています。
【あわせて読みたい記事】
▶︎V2Hの対応車種(EV・PHEV)一覧。バッテリー容量・価格も徹底解説
電気を供給したい日数を基準にバッテリー容量を考える
V2Hシステムを導入する前提でEVやPHEVの車種を選ぶ場合、検討材料となるのはやはりバッテリー容量でしょう。
バッテリー容量が大きければ、その分、長時間、住宅に電気を供給することができます。たとえば、一般家庭での1日あたりの使用電力量を約10kWhと仮定した場合、バッテリー容量が40kWhの日産「リーフ」は約4日ですが、バッテリー容量が66kWhの「アリア」は約6日半も電気を使うことができます。
〈表〉車種に応じた電気が使える日数の目安例
| 車種 | バッテリー容量 | 電気が使える日数(目安) |
| 日産「サクラ」 | 20kWh | 2日間 |
| 日産「リーフ」 | 40kWh | 4日間 |
| 日産「アリア」 | 66kWh | 6.6日間 |
※「リーフ」は40kWhモデル、「アリア」はB6。一般家庭での1日あたりの使用電力量を約10kWhと仮定した場合の試算。V2Hの変換効率などは含まない。
なお、家庭用蓄電池に比べ、大きな容量を割安に確保できるのがEVやPHEVを蓄電池化するメリットです。一般的な家庭用定置型蓄電池は3〜12kWh程度ですが、ほぼすべてのEVやPHEVのバッテリーはこれ以上の容量を有しています。そのため、一般的な家庭用蓄電池並みの性能を求める場合、そこまでバッテリー容量を気にする必要はないでしょう。
バッテリー容量とコストのバランスを考えよう
とはいえ、災害時などのために「電気を蓄える」ことを考慮すると、どうしても大容量のバッテリーを搭載した車体を選びたくなるものです。しかし、バッテリー容量が大きいほど、車体価格は高くなります。また、バッテリーの大きさに比例して、車体重量が増え、電費が悪くなる傾向にもあります。
EVやPHEVを蓄電池化することばかりを考えず、自分のライフスタイルに合った車種を選ぶようにしましょう。EVやPHEVの選び方については、以下の記事をあわせて参考にしてください。
【比較検討】V2H機器を選ぶ基準は?
「系統連系」型か、「非系統連系」型か
V2H機器のタイプは、「系統連系」型と「非系統連系」型の2種類がありますが、「系統連系」型が主流となっています。
〈図〉「系統連系」型

電気の系統はEVやPHEVの大容量バッテリー、電力会社から送られる電気、太陽光発電で作られる電気の3つが考えられますが、「系統連系」型はこの3つのすべてを同時に使うことを可能にします。
〈図〉「非系統連系」型

一方、「非系統連系」型では、同時併用ができず、これらのうち1つを選んで使う形になります。つまり、EVやPHEVから住宅へ電気を供給しているときには、電力会社の電気や太陽光発電からの電気を利用することはできません。
また、「非系統連系」型のV2H機器を選んだ場合、停電時に太陽光発電からEVやPHEVへの充電ができない点にも注意が必要です。
災害時の備えを考えるのなら、現在主流の「系統連系」型のV2H機器を選び、太陽光発電と組み合わせるのが安心といえるでしょう。
【あわせて読みたい記事】
▶︎V2Hの設置費用はいくら? 機器代・工事費までマルッと解説!
コスパは? 電気自動車を蓄電池化するのにかかる費用

V2H機器を購入する場合、本体価格のほかに、設置工事の費用もかります。設置する機種や配線の長さ、太陽光発電の有無などによって価格は変動します。
〈表〉V2H機器の一例
| メーカー | 機種名 | モデル名 | 税込本体価格 |
| ニチコン | EVパワー・ステーション | スタンダードモデル (VCG-663CN3) |
54万7800円 |
| プレミアムモデル (VCG-666CN7) |
98万7800円 ※2023年4月以降出荷分の価格 |
たとえば、上記の機種を選んだ場合、約30万~40万円の工事費がかかります。こうした初期費用がネックになる場合、国や自治体の補助金を申請するのも一手です。
V2Hはカーボンニュートラルに貢献できることから、一定の条件の下、国や自治体からそれぞれ補助金が交付されています。2022年度の国によるV2Hの補助金は、V2H機器の購入費が上限75万円(補助率1/2)、設置工事費は上限40万円で、併せて上限115万円でした。なお、2022年12月現在、すでに申請受付は終了されていますが、補正予算が組まれ国会で可決され、V2H補助金は継続されることになりました。
また、自治体によっては、この国の補助金と併用できる独自の補助金も用意しています。設置を請け負う施工業者が申請をサポートしてくれるケースも多いので、相談してみるとよいでしょう。
【あわせて読みたい記事】
▶︎V2Hの補助金は上限いくら? 国や自治体の制度、注意点を解説
このほか、初期費用が気になるなら、定額利用サービスという選択肢もあります。たとえば、東京電力グループのTEPCOホームテックが提供する定額利用サービス「エネカリ」の場合、月額料金(契約期間10年間)は1万3500円※、工事費を含む導入の初期費用が0円になるので、手軽にV2Hを導入することができます。契約期間中、機器保証や工事保証、自然災害補償がついている点もメリットです。詳しくは、以下をクリックしてみてください。
※ニチコンのプレミアムモデルの場合。2022年11月時点の参考価格。
電気自動車×V2H×太陽光発電を併用するメリットとは?

災害時の備えや電気代の節約などを考える場合、V2H機器に加え、太陽光発電を導入するとシナジー効果も働き、3つのメリットがあります。
【メリット1】災害時の停電に備える
前述のとおり、EVやPHEVの大容量バッテリーは家庭用蓄電池の数倍以上の容量があります。たとえば、一般家庭での1日あたりの使用電力量を約10kWhと仮定した場合、10kWhの家庭用蓄電池が約1日程度の電気しか蓄電できないのに対し、60kWhのEVなら約6日分の電気を供給することが可能です。さらに太陽光発電があれば停電時にも発電した電気を住宅内で使えるのはもちろんのこと、余った電気はEV・PHEVに充電し、充電量を増やすことができるのです。災害時の備えとしては両者とも非常に心強い存在となるでしょう。
【メリット2】電気代の節約につながる
たとえば夜間の電気代が安い料金プランに加入している場合、V2H機器を導入すると、夜間の安い電気をEVに貯めておき、昼間に住宅に戻して使うと、V2H機器の変換ロスはあるにせよ、昼夜間の料金単価差の分だけ、電気代の節約につながります。
また、昨今電気代が高騰していますが、太陽光発電を組み合わせた場合、電力会社から電気を購入するよりも、太陽光発電の電気を住宅で自家消費したほうが、さらに節約になる可能性が高いです。太陽光発電で作った電気をEVに充電すれば、EVの走行コスト(電気代)を削減することにもつながります。
【メリット3】環境負荷をさらに軽減
EVは走行時にCO2(二酸化炭素)などを出さないので、ガソリン車に比べて環境負荷が低いといえます。しかし、充電する電気が火力発電など発電の段階でCO2を排出する電源の場合、もろ手を挙げて環境にやさしいとはいえないのではないかとも一部では言われています。そこで、再生可能エネルギーである太陽光発電の電気を使うことでその懸念も払拭することができ、さらなる環境への貢献ができるでしょう。
EVやPHEVだけでも環境にやさしく、暮らしを豊かにするものですが、太陽光発電やV2Hと組み合わせると、相乗効果があることがわかります。EVやPHEVの購入を検討している人もすでに購入済みの人も、この機会にV2Hや太陽光発電の導入を考えてみてはいかがでしょうか。
【あわせて読みたい記事】
▶︎太陽光発電導入で芽生えた「省エネ意識」。家族が感じた意外なメリット
太陽光発電や蓄電池の導入を手軽にする「エネカリ/エネカリプラス」
太陽光発電や蓄電池の初期費用を抑える方法のひとつとして知っておきたいのが、導入費用がゼロ円(※)になる東京電力グループの「エネカリ/エネカリプラス」です。暮らしのスタイルに合わせて必要な機器を選択した上で、定額サービスを利用できます。
▼「エネカリ」「エネカリプラス」について詳しく知りたい方は、以下のサイトをご覧ください。
※「エネカリプラス」では別途足場代等の費用がかかる場合があります