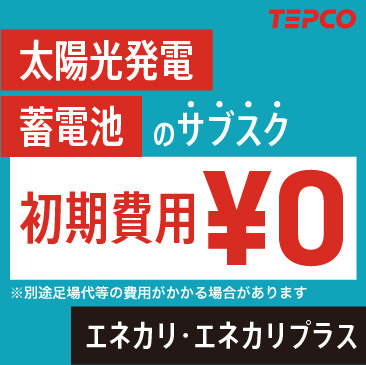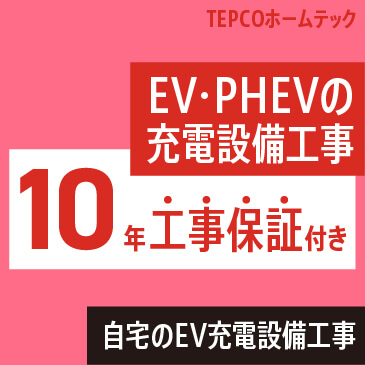有識者にEV業界トレンドを問う「特集 2025年どうなるEV!?」。第3回目のテーマは「EVとPHEV、どちらの市場が優勢になるのか?」です。専門家の生の声を紹介します。
EVとPHEV、どちらの市場が優勢になるのか?
電気のみで走る電気自動車(EV)と、電気とガソリンで走れるプラグインハイブリッド車(PHEV)。世界的に見て、これまで累計販売台数はEVの方が圧倒的に多いものの、近年PHEV人気が増しています。勢力図は変わっていくのでしょうか。専門家たちに疑問を投げかけてみました(以下、回答者名の50音順)。
【あわせて読みたい記事】
▶【図解】EV vs. PHEV、いま売れてるのはどっち?
PHEVがメーカーの開発力と利便性で優勢に
これから数年程度はPHEVが優勢になるだろう。マツダがロータリーエンジンを使ったPHEVを発売するなど、ユニークな商品も出ている。中国BYDの商品力も高い。トヨタもこの分野に力を入れており、日産も北米に投入予定など、メーカーが開発に力を入れている。加えて、充電切れを気にせずに走行できる利便性もある。
回答者

井上久男さん(経済ジャーナリスト)
1988年九州大卒業後、大手電機メーカーに入社。 1992年に朝日新聞社に移り、経済記者として主に自動車や電機を担当。2004年、朝日新聞を退社し、2005年、大阪市立大学修士課程(ベンチャー論)修了。現在はフリーの経済ジャーナリストとして自動車産業を中心とした企業取材のほか、経済安全保障の取材に力を入れている。
PHEVが航続距離と安心感でEVを上回る
燃費のいい内燃機関に乗り慣れた人は、航続距離を気にする。充電してEV走行できることに加え、エンジンでも走れるPHEVは安心感が絶大だ。また、車重も軽い。満充電、満タン状態なら航続距離1,000kmを超えるPHEVも増えてきた。とくに日本は燃費のいいクルマが多いし、山間部や雪国もあるから、しばらくはPHEVが優勢だろう。
回答者

片岡英明さん(モータージャーナリスト)
1954年、茨城県生まれ。自動車専門誌で編集に携わった後、独立してフリーのジャーナリストに。新車のほか、クラシックカーやEVなどの次世代の乗り物にも興味旺盛で、イベント参加することも多い。AJAJ(日本自動車ジャーナリスト協会)会員。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。
PHEV優位。インフラとバッテリー性能がEV普及の鍵
自動車としてのEVとの単純な比較だけでなく、EV業界を取り巻く社会全体の充電環境を考慮すれば、これからの伸び率としてもPHEV優位だと思う。 前述したとおり、ここ数年のEVの盛り上がりとは裏腹に受け皿としてのインフラ整備と、航続距離や耐用年数、交換コストなどバッテリー性能の向上が追いついていない現状を鑑みれば、PHEVを選ぶというユーザー心理は現実的な選択として理解できる。
回答者

楠一成さん(KGモーターズ CEO)
元々、車のパーツなどのアフターマーケット用の企画・開発をする会社を経営。その後、YouTubeチャンネルを開設し、人気チャンネルへと成長させる。2021年から小型モビリティの開発を宣言し、現在ではさまざまな分野のスペシャリストを集めて、事業を拡大。2025年から小型モビリティロボット「mibot」を量産予定。
充電インフラとクルマの魅力、EV・PHEV普及の鍵
EVもPHEVも家庭の充電インフラが必要です、という点で同じくらい「売りにくい」と思っていいでしょう。プリウスのような人気車で、しかも補助金やエネルギーコストを考えたらハイブリッドより実質的に安価なPHEVですら思ったように売れない状況です。問題は魅力のあるクルマかどうかだと考えます。という点でも日本は出遅れるかもしれません。
回答者

国沢光宏さん(モータージャーナリスト)
自動車ジャーナリスト。自動車評論家。現在多くの媒体で執筆活動をしているほか、ラジオ日本とFM群馬でラジオのパーソナリティも行い、車選びからドライビングテクニック、業界ニュースなど、広く深い知識をもつ。運営しているブログサイトでは、専門家も参考にしたくなる、新鮮で豊富な情報を発信している。
低コスト化・高速充電がEVの優位性を決定づける
PHEVのシェアが伸びることはあっても、EVのシェアを抜くことはないと考えます。EVの低コスト化・充電の高速化が進むにつれ、PHEVの存在意義は薄れていくでしょう。日本においては、普通車はPHEVが優位ですが、この傾向は普及価格帯のEVが増えない限り続くと思います。スズキ「eビターラ」がどの程度売れるかによりますが、日本への割り当て台数が少ないとの報道もあります。
回答者
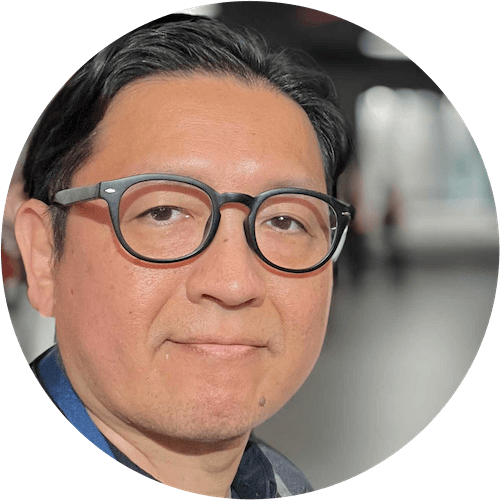
佐藤耕一さん(モータージャーナリスト)
自動車メディアの副編集長として活動したのち、IT業界に転じて自動車メーカー向けビジネス開発に従事。2017年ライターとして独立。自動車メディアとIT業界での経験を活かし、CASE領域・EV関連動向を中心に取材・動画制作・レポート/コンサル活動を行う。日本自動車ジャーナリスト協会会員。
国産車はPHEV、輸入車はEVが優勢
日本車はPHEV、輸入車はEVが優勢になると思います。日本車は、これまでも常にEVよりもPHEVが優勢でした。新たに魅力的なEVが登場しない限り、状況は変わらないでしょう。輸入車は日本車とは逆に、常にPHEVよりもEVが優勢でした。これも変わらないはず。輸入車でEVが優勢なのは、単純にEVの方がラインナップが豊富だったからです。輸入車にもPHEVのラインナップが増えれば、状況は、また変わるはずです。
回答者

鈴木ケンイチさん(モータージャーナリスト)
1966年生まれ。茨城県出身。國學院大学経済学部卒業後、雑誌編集者を経て独立。レース経験あり。日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員。
PHEVは世界で躍進しているものの日本では限定的
日本国内ではPHEVのシェアの伸び方は限定的になると推測。理由はハイブリッド車の販売シェアが大きく、現状ラインナップされているPHEVのコストの高さを考慮に入れると、多くのユーザーはハイブリッド車を選択し続けるのではないか。
グローバルでは最大市場の中国でEREV(※編集部注)を含むPHEVの販売シェア率が足元で上昇しており、2025年シーズンもPHEVの販売台数が順調に伸びていく見込みであることから、世界全体でのPHEVシェア率も上昇。BEVとPHEVの販売シェア率は概ね6:4程度で推移するのではないかと推測。
回答者

高橋優さん(EV専門ジャーナリスト)
1996年、埼玉県生まれ。2020年よりYouTubeチャンネル『EVネイティブ【日本一わかりやすい電気自動車チャンネル】』を運営。世界の最新EVニュースをわかりやすく解説している。新型EV情報はもちろん、充電インフラ、バッテリーの最新情報、国内外のEV事情など、深く、広く情報を網羅。同時にさまざまなEVの1000キロチャレンジ、極寒車中泊など、EVの運用を体を張ってテスト。ユーザー目線の情報も数多く発信している。
注:「Extended Range Electric Vehicle」の略で、レンジエクステンダーEVとも呼ばれる。EVをベースとしながら、航続距離延長を目的に発電用のエンジンを搭載する車のことで、統計上はPHEVに区分されることが多い。
PHEVが当面優勢だがEVシフトは将来的に不可避
トヨタが現状の日本市場ではEVよりもPHEV車種を増やしており、中国のBYDもPHEVに注力するようになっているので、当面はPHEVが優勢に見える状況になりそうです。とはいえ、電気駆動の気持ちよさや脱化石燃料の意義を思えばPHEVはあくまでもEVシフトへのステップです。集合住宅の充電設備や経路充電、目的地充電の環境が整うに従って、エンジンを併用するメリットは減退していくと思っています。
回答者

寄本好則さん(EVsmartブログ編集長)
コンテンツ制作プロダクション三軒茶屋ファクトリー代表。一般社団法人日本EVクラブのメンバー。2013年にはEVスーパーセブンで日本一周急速充電の旅を達成。ウェブメディアを中心に電気自動車と環境&社会課題を中心とした取材と情報発信を展開。電気自動車情報メディアや雑誌特集などに多く寄稿している。著書に『電気自動車で幸せになる』(Kindle)など。
PHEV優勢はいつまで続く? 専門家の見解はEVの進化に期待
当面はPHEVのほうが勢いがよく、市場をリードするという意見が多いようです。ただし将来的にはEVが主流となる可能性が高いという見方もあります。
PHEVは、航続距離の長さや充電インフラへの依存度が低い点で、現状ではEVよりも優位性を持つと評価されています。しかし、EVの低コスト化や充電技術の進化が進めば、PHEVのメリットは薄れていくと予想する専門家も少なくありません。
最終的にEVとPHEVのどちらが支持されるのかは、EVの技術革新、充電インフラの整備状況、そしてユーザーのニーズの変化によると言えるでしょう。
※本記事の内容は公開日時点での情報となります