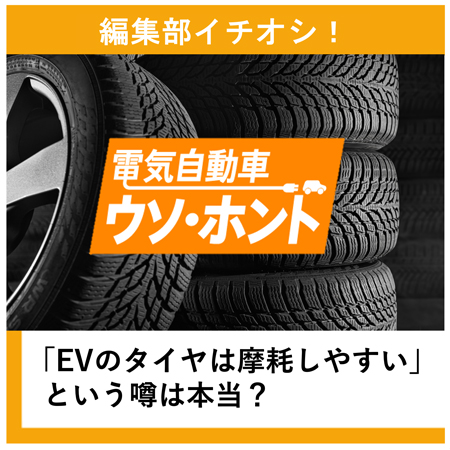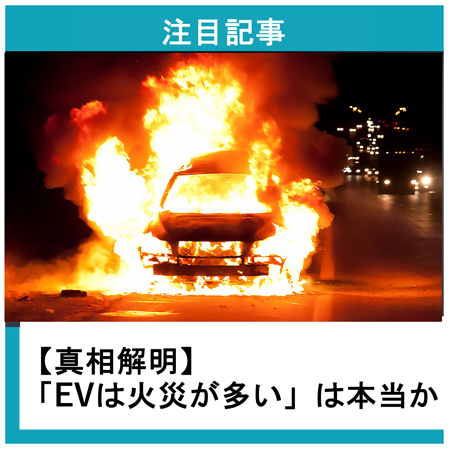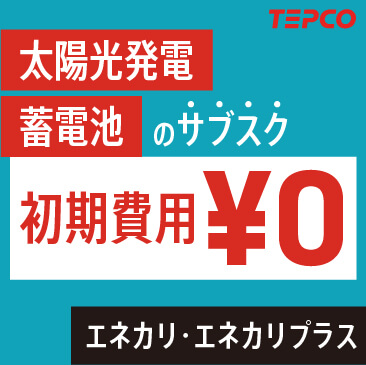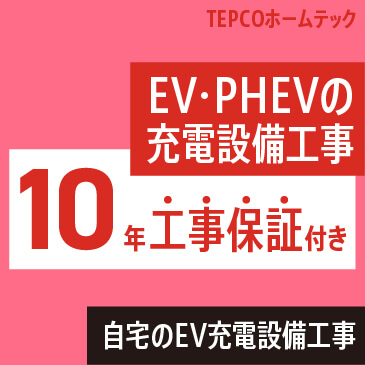軽自動車の新型商用EVが今秋に発売されるなど、電気自動車(EV)のラインナップが増えてきました。ガソリン車からEVへの買い替えを検討している人も多いことでしょう。自動車ジャーナリストの国沢さん監修のもと、現在購入可能なEVを「価格」「航続距離」などの項目ごとにチェックしながらEV DAYS編集部が紹介します。
※この記事は2024年1月11日に公開した内容をアップデートしています。
- EV購入時にチェックしたい3つのポイント
- 【価格帯で見るEV】このくらいの予算なら、何に乗れる?
- [予算500万円未満]比較的リーズナブル、でも、大満足なEVは?
- [予算500万円以上]高くても性能のいい車に長く乗りたい人向けの高性能EVは?
- 4WDのEVのおすすめ車種は?
- 100万円以下で購入できる中古EVのおすすめ車種は?
- EV購入時には補助金の申請受付終了見込み時期に注意
- 【航続距離で見るEV】1回の満充電で長く走れるのは?
- 自分の「予算」と「ライフスタイル」に合ったEVを見つけよう
EV購入時にチェックしたい3つのポイント

車を選ぶときには「価格はどの程度か」「どんなシーンで使いたいのか」「どれくらいの頻度で使うのか」「どんなボディタイプが好きか」などの条件で購入を検討することが多いと思います。
しかし、EVの場合、それに加えて1回の満充電で走行できる航続距離も重要な要素となります。また、同じ車種でもバッテリー容量がグレードによって異なっていたり、最近では数千回の繰り返し充電に耐える長寿命バッテリーを搭載する車種が登場したりと、これからはますます「バッテリー選び」の重要度も増してくるでしょう。
ここではEV購入時にチェックしておきたいポイントを「予算」「航続距離」「ボディタイプ」の3つに絞って紹介します。
チェックポイント①補助金額と予算
車両価格だけを見ると、EVはガソリン車などに比べて割高に感じます。また、EVは価格帯ごとに購入可能な車種がある程度限られているため、EV購入を検討しているなら「予算」がとても重要です。
ただし、EVは購入時に国や自治体の補助金を利用できる場合が多いほか、税金の優遇措置などもあります。車両価格がガソリン車などに比べて割高だとしても、それらを利用することで、通常の車両価格よりかなり安くEVを購入することが可能です。
なお、2024年度の国によるEV補助金の上限額は85万円、小型・軽自動車のEVやプラグインハイブリッド車(PHEV)の補助金上限額は55万円となっていますが、全車種が上限額を受けられるわけではありません。「自動車分野のGX(グリーントランスフォーメーション)実現の必要な価値」に基づき、充電インフラ整備や製品ライフサイクル全体でのCO2(二酸化炭素)排出量削減など、EV普及や環境に対するメーカーの取り組みが総合的に評価されて補助金の額が算出されます 1)。
補助金額は上記の評価で段階的に決まり、車種によって交付される補助金額が変わりますので注意しましょう。補助金や税制優遇措置についてもっと詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
また、電気を使って走るEVはガソリン車よりも走行コストがかからず、部品数が少ないのでメンテナンス代も安く済みます。車両価格が高くてもランニングコストが安いというメリットもあるのです。
【あわせて読みたい記事】
▶【2024年度】電気自動車(EV)の補助金は上限いくら? 国や自治体の制度、注意点を解説
チェックポイント②航続距離
次にチェックしたいのが「航続距離」です。航続距離とは、1回の満充電によって車が走行できる距離のことで、正式には「一充電走行距離」と言います。EVは同じ車種でも搭載されているバッテリーの容量などによって航続距離が異なり、それによって車両価格も変わってきます。
たとえば、日産「リーフ」にはバッテリー容量が40kWhのモデルと60kWhのモデル(「リーフe+」)があり、航続距離は前者が322km、後者が450km。当然ながら航続距離が長いほうが車を使ううえで便利ですが、両者にはおよそ120万円の価格差があります。
安価なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)電池を搭載する中国メーカーのEVの登場などにより、今後は容量の大きいバッテリーを搭載した車種の価格も安くなっていくと予想されます。使い方にもよりますが、現時点では40kWh以上のバッテリー容量がある車種を選ぶと「充電切れ」や「電欠」をあまり心配せずに使うことができるでしょう。
もっとも、ガソリン車などと同様に、EVの航続距離もカタログ値どおりにはいきません。冷暖房の使用やバッテリーの温度管理などにも電気を消費するため、どの車種を選んでも実際の航続距離は感覚的にはカタログ値の7~8割程度だと考えたほうがいいでしょう。
チェックポイント③ボディタイプ
これから普及していくEVはガソリン車などに比べると車種がまだ少なく、選べるボディタイプがある程度限定されます。
たとえば、軽乗用車のEVは日産「サクラ」と三菱「eKクロスEV」の2車種がありますが、いずれもヒンジドアのハイトワゴンのみです。EVのミニバンも2024年6月時点で国内販売されていません。現在のEVの主流のボディタイプはSUVで、今後しばらくこの傾向が続くと考えられます。
SUVが主流となっているのはEVの構造とも関係しています。EVはバッテリーをフロア下に敷き詰めるように搭載しますが、SUVは車高が高く、ボディ形状的にセダンなどに比べて大きなバッテリーを搭載しやすいのです。また、重いバッテリーを床下に搭載することで走りが安定するといったメリットもあります。SUVはEVに限らず、現在もっとも人気の高いボディタイプだからという理由もあるでしょう。
予算を大きく引き上げれば、購入を検討している方が選べるボディタイプの種類も広がっていきますが、現状ではEVのボディタイプはある程度限定されることを理解しておいたほうがいいでしょう。
【価格帯で見るEV】このくらいの予算なら、何に乗れる?
[予算250万円程度]ガソリン車と遜色ない価格で購入できるリーズナブルな軽EV
EV選びは予算が大切とお話しましたが、実際のところ、どれくらいの予算があればEVを購入できるのでしょうか。まず数あるEVのなかでもっとも車両価格が安い「軽EV」から紹介します。
〈軽EVの2車種〉※メーカー50音順
| 車種 | 価格 |
| 日産「サクラ」 | 259万9300円〜2) |
| 三菱「eKクロスEV」 | 256万8500円〜3) |
※価格は各メーカーの公式サイトより。すべて税込価格です。
Ⅰ.日産「サクラ」 259万9300円~

2022年6月に発売された「サクラ」は日産にとって初となる軽EVです。「X」「G」の2グレードが用意され、このうち価格の安い「X」グレードは259万9300円となっています。
ガソリン車の軽自動車と比べると少し高いと感じるかもしれませんが、約260万円という車両価格は従来の国産EVより100万円以上安くなっています。加えて、購入時に国や自治体の補助金などを利用すれば、ガソリン車と同等以上の安さで購入することが可能です。
ボディタイプは軽自動車で主流のハイトワゴンで、内外装のデザインに日産のフラッグシップEV「アリア」譲りの意匠を採用。全体的に軽EVとは思えない上質感があり、「サクラ」は軽自動車全体のなかでも販売台数でトップ10に入ることもある人気車種となっています。
Ⅱ.三菱「eKクロス EV」 256万8500円~

「eKクロス EV」は、三菱のSUVテイストのハイトワゴン・シリーズ「eKクロス」の一員として誕生した軽EVです。「G」「P」の2グレードが用意され、このうち価格の安い「G」グレードの車両価格は256万8500円となっています。
「eKクロス EV」は日産「サクラ」と基本メカニズムを共有する兄弟車で、性能面に大きな違いはありません。どちらもバッテリー容量は20kWhで、フル充電の航続距離は180km。航続距離が180kmと聞くと少し短いと思うかもしれませんが、実際の航続距離がカタログ値の7~8割程度だとしても、買い物や送り迎えなど近距離走行が多い人には十分な性能です。
メカニズムは共通でも、デザインや車の特徴は「サクラ」と少し異なります。「サクラ」が日産のフラッグシップEV「アリア」譲りの上質感を打ち出しているのに対し、「eKクロス EV」はSUVテイストを前面に押し出している点が特徴です。同じ価格帯のEVの場合、こうしたキャラクターの違いに注目するのもいいかもしれません。
参考資料
2)日産「サクラ」
3)三菱「eKクロスEV」
[予算500万円未満]比較的リーズナブル、でも、大満足なEVは?
普通車のEVのなかでは、比較的お手頃な価格で購入できるのが「予算500万円未満」の車種です。国産EVの代名詞的存在の日産「リーフ」から、ヒョンデ「KONA」やBYD「DOLPHIN」といった輸入車のコンパクトカーまで、500万円未満で購入可能なEVを紹介します。
〈500万円未満のEV車種例〉※メーカー50音順
| 車種 | 価格 |
| 日産「リーフ」 | 408万1000円~4) |
| ヒョンデ「KONA」 | 399万3000円〜5) |
| BYD 「DOLPHIN」 | 363万円~6) |
| マツダ「MX-30 EV MODEL」 | 451万円~7) |
※価格は各メーカーの公式サイトより。すべて税込価格です。
Ⅰ.日産「リーフ」 408万1000円~

日産「リーフ」は2010年に普通車のEV市場の先陣を切って登場した国産EVの代名詞的車種で、現行モデルは2代目です。以前は300万円台から購入可能でしたが、2022年12月に価格改定が行われ、車両価格は標準グレード(X)で約408万円〜になりました。
バッテリー容量は40kWhと60kWh(「リーフe+」)があり、航続距離はそれぞれ322km、450km。いまでは性能面に目立った特徴はありませんが、初代モデルの発売からすでに十数年が経過していますから、その信頼性の高さが「リーフ」のポイントです。
【スペック確認はこちら!】
▶︎EV車種一覧ページ 日産「リーフ」
Ⅱ.ヒョンデ「KONA」 399万3000円~️

韓国の大手車メーカー「ヒョンデ」が2023年11月に販売を開始した「KONA(コナ)」は、ベースグレードであれば400万円を切る車両価格を実現したコンパクトSUVスタイルのEVです。
日本向けのグレードは、バッテリー容量が48.6kWhの「Casual」と64.8kWhの「Voyage」「Lounge」「Lounge Two-tone」の計4モデルが用意され、航続距離は「Casual」が456km、「Voyage」が625km、「Lounge」「Lounge Two-tone」が541km(すべてWLTCモード/自社測定値)となっています。
また、ヒョンデは日本国内に正規ディーラーを持たないため、「KONA」は「IONIQ 5」と同様に、ヒョンデの公式ウェブサイト及びアプリを通じたオンライン販売のみとなっているのも特徴的です。
Ⅲ.BYD「DOLPHIN」 363万円〜

グローバル販売台数でテスラと覇権争いを繰り広げる中国のEVメーカー、BYDが日本向けラインナップ第二弾として2023年9月に発売したのがコンパクトEVの「DOLPHIN(ドルフィン)」です。363万円〜という車両価格は、2024年6月時点で国内販売される普通乗用車のEVのなかでもっとも低価格となっています。
ベースグレードと「Long Range」の2グレードが用意され、航続距離はそれぞれ400kmと476km。BYDのEVの最大の特徴とも言える劣化に強いリン酸鉄リチウムイオン(LFP)電池を採用し、V2H/V2Lに対応しているのも「DOLPHIN」のポイントでしょう。また、コンパクトなボディながら最大5名が乗車可能なので使い勝手もよさそうです。
【あわせて読みたい記事】
▶BYD ドルフィン。驚異のコスパを誇るファミリー向けコンパクトEV
▶V2Hの対応車種(EV・PHEV)一覧。バッテリー容量・価格も徹底解説
【スペック確認はこちら!】
▶EV車種一覧ページ BYD「DOLPHIN」
Ⅳ.マツダ「MX-30 EV MODEL」 451万円~

「MX-30 EV MODEL」はSUVタイプのスタイリングをもつマツダにとって初の量産EVです。内装にコルクやペットボトルなどサスティナブルな素材を用いており、ドアにはセンターピラーのない観音開きの「フリースタイルドア」が採用されています。
2022年10月に一部改良が行われ、バッテリー容量35.5kWhと航続距離256kmに変更はありませんが、ラゲッジルームにAC1500Wコンセント、フロントコンソール用にAC150Wコンセントがそれぞれ追加設定されました。また、V2H/V2L機能も追加され、自然災害の多い地域にお住まいの方や、アウトドアライフを楽しみたい人にとって、こうした外部給電機能はうれしいポイントでしょう。
参考資料
4)日産「リーフ」
5)ヒョンデ「KONA」
6)BYD「DOLPHIN」
7)マツダ「MX-30 EV MODEL」
[予算500万円以上]高くても性能のいい車に長く乗りたい人向けの高性能EVは?
EVの購入やガソリン車からの買い替えを検討している人には「高くても性能のいいEVに長く乗りたい」と考えている方もいることでしょう。世界市場を見ても売れ筋のEVは500万〜600万円台の車種となっており、メーカーもこの価格帯の車の開発にもっとも力を注いでいます。500万円以上のEVにはどんなものがあるのでしょうか。日本で購入できる500万〜600万円台のEVを中心に紹介します。
〈500万円以上のEV車種例〉※メーカー50音順
| 車種 | 価格 |
| アウディ「Q4 e-tron」 | 638万円~8) |
| テスラ「モデルY」 | 533万7000円〜9) |
| トヨタ「bZ4X」 | 550万円~10) |
| 日産「アリア」 | 659万100円~11) |
| BMW「iX1」 | 718万円~12) |
| フィアット「500e」 | 553万円〜13) |
| フォルクスワーゲン「ID.4」 | 514万2000円~14) |
| プジョー「e-208」 | 512万4000円~15) |
| ボルボ「EX30」 | 559万円~16) |
| メルセデス・ベンツ「EQB」 | 822万円~17) |
※価格は各メーカーの公式サイトより。すべて税込価格です。
Ⅰ.アウディ「Audi Q4 e-tron」 638万円~

従来のアウディ「e-tron」シリーズは車両価格1000万円超のハイパフォーマンスモデルが中心でしたが、「e-tron」シリーズの第3弾として登場した「Audi Q4 e-tron」は638万円〜と、そうした「e-tron」シリーズのイメージを覆す車両価格となっています。
コンパクトSUVなので、ボディサイズは日産「アリア」などとほぼ同じです。バッテリー容量は82kWhで、航続距離は594kmと十分。同等のサイズとメカニズムを持ち、クーペSUVスタイルの「Audi Q4 Sportback e-tron」もラインナップされます。こちらの車両価格は730万円~。
【あわせて読みたい記事】
▶︎Audi RS e-tron GT。美しさと性能を追求したEV時代のグランツーリスモ
【スペック確認はこちら!】
▶︎EV車種一覧ページ アウディ「Audi Q4 e-tron」
Ⅱ.テスラ「モデルY」 533万7000円〜

世界のEV市場をリードするテスラにおいて、SUVタイプのエントリーモデルとなるのが「モデルY」です。「モデルY」は2023年に販売されたガソリン車やハイブリッド車(HEV)も含めたすべての車のうち、車名別において世界で一番多く売れたことでも有名です。
航続距離507kmのRWDモデルと、航続距離595kmとなるデュアルモーターAWDの「パフォーマンス」、同605kmの「ロングレンジ」がラインナップされます(バッテリー容量は非公開)。
車両価格は600万円を切りますが、テスラの代名詞ともいえる先進運転支援システム「オートパイロット」の上級版「エンハンスト オートパイロット」や、最上級版「フルセルフドライビング ケイパビリティ」といったオプションは、それぞれ43万6000円、87万1000円となっていますので注意しましょう。
テスラはその時々の市況などに合わせて車両価格がよく変更されます。2024年6月時点での価格は約533万円~ですが、購入の際には公式サイトで価格をよく確認したほうがいいかもしれません。
Ⅲ.トヨタ「bZ4X」 550万円~

トヨタ「bZ4X」はスバルと共同開発されたSUVタイプのEVです。当初はリース販売のみで、個人ユーザーにはサブスクリプションサービス「KINTO」を通じて提供されていましたが、2023年11月の一部改良に合わせて一般販売も開始されました。価格は「G」グレードのFWDが550万円、4WDが600万円、「Z」グレードのFWDが600万円、4WDが650万円となっています。
バッテリー容量は71.4kWh、航続距離は540〜567km。1回の充電で走行できる距離はアウディ「Q4 e-tron」やテスラ「モデル3」にも引けを取りません。
Ⅳ.日産「アリア」659万100円~

初代「リーフ」から日産が10年以上にわたって積み重ねてきたEV開発のノウハウと技術を惜しみなく注ぎ込んだ新型EVとして、2022年5月に登場したのが「アリア」の標準グレード「B6」です。
未来を感じさせるインテリアとエクステリア、それでいて随所に使われた「桜」や「組子」といった和のテイスト、ラウンジのような室内など、デザイン面を見ても日産の自信がうかがえます。
「B6」のバッテリー容量は66kWhで、航続距離は470km。ベースモデルのほか、4WDモデルの「B6 e-4ORCE(イー・フォース)」、バッテリー容量が91kWhの「B9」とその4WDモデルである「B9 e-4ORCE」、さらに「B9 e-4ORCE プレミア」「NISMO B6 e-4ORCE」「NISMO B9 e-4ORCE」の計7モデルがラインナップされています。特に「B9」は航続距離が640kmと国産EV最長を誇ります。
V.BMW「iX1」 718万円〜

BMWはEV専用モデルの「iX」に加え、「iX1」「iX2」「iX3」「i4」「i5」「i7」と、ガソリン車とボディを共用するEVを多数ラインナップしています。なかでも、もっとも新しく、718万円〜とBMWの中では比較的手が届きやすいのが、コンパクトSUV「X1」のEV版となる「iX1」です。
全長4500×全幅1835×全高1625mmのボディサイズはボルボ「XC40 Recharge」やBYD「ATTO 3」などに近く、バッテリー容量66.5kWh、航続距離465kmもそれらの車種と同等。ただし、「iX1」は前後2モーターの4WDのみとなっています。
「iX1」はアダプティブクルーズコントロールなどの運転支援機能も充実。モデルとしては「iX1 xDrive30」の1機種となりますが、モダンな「XLine」にスポーティな「M Sport」と、内外装のテイストを選択可能です。
VI.フィアット「500e」 553万円〜

2022年6月に日本で販売を開始した「500e」はフィアット初となるピュアEVです。EVならではの新たなドライバビリティを味わえる一方、歴代「500(チンクエチェント)」から受け継ぐ唯一無二のユニークなデザインは基本的に変わっていません。
ボディサイズは全長・全幅・全高ともに「500」よりやや大きく、バッテリー容量は42kWh、航続距離は335km、車両価格は553万円〜となっています。なお、2023年10月にはフィアットのハイパフォーマンスブランド・アバルト版「500e」も国内で販売開始しました。

アバルト版にもハッチバックとカブリオレの2モデルが用意され、前者の「500e Turismo ハッチバック」のバッテリー容量は42kWh、航続距離は303km、車両価格は615万円〜となっています 15)。
【あわせて読みたい記事】
▶イタリアの名車、チンクエチェント。EVになっても変わらない、圧倒的魅力
▶アバルト500e。小さくても絶大な存在感!“電気サソリ”の革新的な走り
【スペック確認はこちら!】
▶EV車種一覧ページ フィアット「500e」
▶EV車種一覧ページ アバルト「500e」
VII.フォルクスワーゲン「ID.4」 514万2000円〜

フォルクスワーゲン「ID.4」は、同社のEVブランド「ID」シリーズの日本導入第一弾として2022年11月に登場したEV専用モデルです。全長4585mm×全幅1850mm×全高1640mmのボディサイズは日産「アリア」とほぼ同じで、室内は後席の足元も広々としています。
エントリーグレードの「Lite」と上位グレードの「Pro」の2タイプがあり、「Lite」は最高出力125kWのモーターに52kWhのバッテリーを組み合わせ、航続距離は435km。「Pro」は同150kWのモーターに77kWhのバッテリーを組み合わせ、航続距離は618kmです。
「Lite」と「Pro」はEVシステムだけでなく装備にも大きな違いがあり、「Pro」には専用エクステリアやパノラマガラスルーフ、パワーシート、パワーテールゲート、20インチタイヤなどが標準装備されます。
VIII.プジョー「e-208」 512万4000円~

フランス車のプジョー「e-208」は、日産「リーフ」よりもひと回り小さいコンパクトカーのEVです。登場当初は300万円台から購入可能でしたが、原材料の価格高騰などのコスト上昇にともなって2022年夏以降は何度か価格が改定され、現在は「e-208 GT」のみのラインナップで512万4000円〜となっています。
バッテリー容量は50kWhで、航続距離はコンパクトカーのEVとしては比較的長い395km。値上げにより当初のようなお手頃感は薄れましたが、比較的手の届きやすいEVといえます。なお、「e-208」は2023年7月に欧州仕様の大幅な改良が行われ、今後日本仕様も新型に切り替わることが予想されます。
IX.ボルボ「EX30」 559万円

2023年8月に発表された「EX30」は、ボルボ史上最小のSUVです。「EX30」以前の「C40 Recharge」「XC40 Recharge」の2台のEVが ガソリン車との共通プラットフォームだったのに対し、「EX30」はEV専用プラットフォームを採用しているのが大きな特徴です。
日本仕様はバッテリー容量69kWh、航続距離560kmの1タイプのみですが、本国にはより安価なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリー仕様もあり、価格面でもバッテリー寿命の面でもこちらの日本導入が期待されるところでしょう。とはいえ、559万円という価格は日産「リーフe+」と同等程度。それでいて航続距離が長く、ボルボらしい先進安全装備も次世代型が搭載されています。
なお、既存の「C40 Recharge」と「XC40 Recharge」の2台は2023年3月にマイナーチェンジを実施し、駆動方式がFWDと4WDから、RWDの1タイプへと変更されています。️
【あわせて読みたい記事】
▶ボルボ・EX30。環境性能と美しさを両立した最先端コンパクトEV
▶ボルボXC40 Recharge。使い勝手が向上したベストセラーのEV版
【スペック確認はこちら!】
▶EV車種一覧ページ ボルボ「EX30」
X.メルセデス・ベンツ「EQB」 822万円〜️

メルセデス・ベンツ「EQB」は、コンパクトSUV「GLB」のEV版です。ガソリンモデルと基本設計は共通ですが、EVでは希少な3列シートの7人乗りモデルとして人気を集めています。
「EQB 250」と4WDの「EQB 350 4MATIC」の2グレードがあり、バッテリー容量はどちらも66.5kWh。航続距離はそれぞれ520km、468kmです。各種の先進運転支援システムも装備され、価格は「EQB 250」が822万円、「EQB 350 4MATIC」は906万円となっています。
大人数が乗れる3列シートを搭載するため、ボディサイズは全長4685×全幅1835×全高1705mmとコンパクトSUVとしては全長が長めですが、ミドルクラスSUVのトヨタ「ハリアー」よりは短いので、相対的には比較的コンパクトと言えるでしょう。
参考資料
8)アウディ「Q4 e-tron」
9)テスラ「モデルY」
10)トヨタ「bZ4X」
11)日産「アリア」
12)BMW「iX1」
13)フィアット「500e」
14)アバルト「500e」
15)フォルクスワーゲン「ID.4」
16)プジョー「e-208」
17)ボルボ「EX30」
18)メルセデス・ベンツ「EQB」
4WDのEVのおすすめ車種は?
4WDには雪道や悪路走行に強いイメージがあるかもしれません。いわゆる「生活四駆」と呼ばれる車です。しかし、EVの場合はトルクフルなEVのパワーをタイヤが受け止めるために四輪駆動としている場合が多いです。つまり「走りのための四駆」というわけです。
そのため、4WDのEVはスポーツモデルが中心で、高価格な車種が多くなっています。そのなかでも比較的手の届きやすい車種を以下の記事で紹介していますので、興味がある方は読んでみてください。
【あわせて読みたい記事】
▶︎電気自動車の4WDのおすすめは? 自動車ジャーナリストが推奨する10車種
100万円以下で購入できる中古EVのおすすめ車種は?

ここまで見てきてわかるように、軽EVを除く多くのEVは車両価格が400万円以上します。市場全体のボリュームゾーンも500万〜600万円台ですから、ガソリン車からの買い替えを躊躇する人も多いかもしれません。その場合、中古車のEVを購入する方法もあります。
EVは年式が新しい車種が多いので中古価格が比較的まだ高く、また中古車のEVは新車のように補助金も利用できないのであまりおトク感はありません。ただし、発売から10年以上が経過し、販売台数も多い日産「リーフ」は別です。価格も安いので、EV購入検討層の選択肢のひとつになるはずです。
中古価格が安いと「バッテリーが劣化しているのでは?」と思うかもしれませんが、日産は「リーフ」のバッテリーに「8年間または走行距離16万km※」の容量保証をつけています19)。5年落ちの「リーフ」でも大きな性能低下を心配せず乗ることができるでしょう。
また、仮にバッテリー性能が低下していても、EVを近距離専用の車と割り切れば長い航続距離は必要なくなります。買い物や送迎などの普段使いに限定すれば、バッテリーの保証期間が過ぎた初期型の「リーフ」を100万円以下で購入して乗ることも可能になります。
※新車登録から8年間または走行距離16万kmまでのどちらか早い方。24kWhバッテリー搭載車は5年間または10万kmまで。
なお、最近はお手頃価格のテスラ「モデル3」も中古車市場に増えてきましたが、テスラ車はメンテナンス面が未知数で、整備費用が高額になる可能性があります。また、正規ディーラーを持たないため整備拠点が少ないという面もあります。価格だけではなく、そうしたデメリットも理解したうえで総合的に検討したほうがいいでしょう。
参考資料
19)日産リーフ公式サイト「メンテナンス・サポート」
【あわせて読みたい記事】
▶︎2023年は「中古EV元年」かも。EVの中古車市場、果たしてどうなる?
EV購入時には補助金の申請受付終了見込み時期に注意
EVの購入を具体的に検討している人でしたら、必ず利用したいのが国や自治体の補助金です。2024年度の国のEV補助金の一例を挙げると、軽EVは最大55万円、普通車EVは最大85万円となっています20)。国の補助金に加えて地方自治体からの補助金もあるため、地域や条件によってはEVの購入時に100万円以上を補助されることもあります。
注意する必要があるのは、前述のとおり、自動車メーカーのEV普及や環境に対する取り組み方によって補助金額が変わることです。また、予算には上限があり、補助金の申請が多い場合は早めに予算が消化されるケースがあります。いま新車の納期が全体的に長くなっていますから、EV購入を検討しているなら、補助金の予算が消化される前に行動したほうがいいでしょう。
【あわせて読みたい記事】
▶︎電気自動車(EV)の補助金は上限いくら? 国や自治体の制度、注意点を解説
【航続距離で見るEV】1回の満充電で長く走れるのは?

ここまで価格を中心に車種を紹介してきましたが、価格より性能面が気になるという人もいることでしょう。なかでもEV購入を検討している人から「航続距離が短い」という心配の声をよく聞きます。
しかし、現在のEVは搭載するバッテリーの容量が大きく、性能も向上しており、ほとんどの車種が1回の満充電で200〜600kmの走行が可能になっています。航続距離が200kmあれば、買い物や送り迎え、近場のドライブではまったく問題ありません。また、航続距離600kmなら、かなりのロングドライブでも途中で充電することなく走り続けることができます。
メーカーが公表している数値をもとに「航続距離が600km以上あるEV」をリストアップしました。
〈航続距離が600km以上あるEV例〉※メーカー50音順
| 車種 | バッテリー容量 | 航続距離※ |
| アウディ「Q8 Sportback 55 e-tron quattro S lineレンジプラスパッケージ装着車」 | 114kWh | 619km 21) |
| テスラ「モデル 3 ロングレンジ」 | 非公開 | 706km 22) |
| テスラ「モデル Y ロングレンジ」 | 非公開 | 605km 10) |
| テスラ「モデル S」 | 非公開 | 634km(WLTPモード) 23) |
| 日産「アリア B9」 | 91kWh | 640km 12) |
| ヒョンデ「IONIQ5 Voyage/Lounge」 | 72.6kWh | 618km(WLTCモード自社測定値) 24) |
| BMW「i4 eDrive40」 | 83.9kWh | 604km 25) |
| BMW「i7 xDrive50」 | 105.7kWh | 652km 26) |
| BMW「iX xDrive50」 | 111.5kWh | 650km 27) |
| フォルクスワーゲン「ID.4 Pro」 | 77kWh | 618km 16) |
| メルセデス・ベンツ「EQE 350+」 | 90.6kWh | 624km 28) |
| メルセデス・ベンツ「EQS 450+」 | 107.8kWh | 700km 29) |
※注記がないものは「WLTCモード(国土交通省審査値)」の値
ご覧のように、上位にはテスラやBMW、メルセデス・ベンツといった高級車のEVが並びました。これはテスラや欧州のプレミアムメーカーのEVが国産車のEVより大きな容量のバッテリーを搭載しているからです。
アウディ「Q8 Sportback e-tron」やテスラ「モデル S」、BMW「i7」「iX」、メルセデス・ベンツ「EQE」「EQS」は1000万円超の高級車ですが、購入予算がかかっても航続距離を伸ばしたいという人には、こうした車種がおすすめかもしれません。
参考資料
21)アウディ「Audi Q8 Sportback e-tron」
22)テスラ「モデル 3」
23)テスラ「モデル S」
24)ヒョンデ「IONIQ5」
25)BMW「i4」
26)BMW「i7」
27)BMW「iX」
28)メルセデス・ベンツ「EQE」
29)メルセデス・ベンツ「EQS」
自分の「予算」と「ライフスタイル」に合ったEVを見つけよう

日本国内で購入できるEVをさまざまな条件で紹介しましたが、EV購入を検討中の方に知っておいてほしいのは「EVはガソリン車やハイブリッド車と購入する際の検討ポイントが異なる」ことです。
EVはガソリン車と比べて航続距離が短いため、長距離移動の多い人はバッテリー容量の大きいEVを選んだほうがいいでしょう。逆に買い物や送迎などの普段使いが多い人は、価格が安くてバッテリー容量が小さいEVで十分です。EVはガソリン車より車種が少ないですから、こうしたポイントを押さえることが重要となります。
国や自治体の補助金を利用すれば100万円台で購入できる軽EVが登場したことで、EVがより身近な存在になってきました。ホンダ「N-VAN」のEVモデル「N-VAN e:」が2024年秋に発売を予定されるなど、今後は軽EVの選択肢も増えていくと予想されます。
EVは日々進化しており、これからも安価で性能のいい車種がどんどん発売されることでしょう。補助金を含め、EVに関する最新の情報に耳を傾け、自分の予算とライフスタイルに合ったEVを探してみてください。
※本記事の内容は公開日時点での情報となります