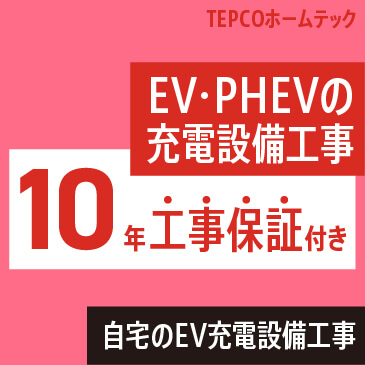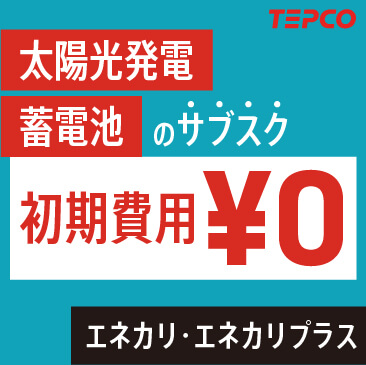日本車を代表する伝統のブランドといえば、トヨタのクラウンです。その時代の技術の粋を集め、快適性だけでなく走りにも強くこだわっています。誕生から70年を前に、クラウンは大きく変わりました。多くの仲間が生まれたなかで、もっとも異色とも言えるプラグインハイブリッドシステム(PHEV)を採用したクラウンスポーツRSの真の実力を、歴史をたっぷり踏まえながらモータージャーナリストの片岡英明さんがレポートします。
歴代クラウンをダイジェストで振り返る
日本の乗用車のなかでもっとも長い歴史を誇るクラウンが誕生したのは1955(昭和30)年である。その歴史をひもときながら、16代を数えるクラウンの魅力と先見性について語っていこうと思う。少し長い話になるが、まずはその歴史を振り返っていきたい。

初代クラウンは観音開きドアを採用し、乗降性も重視したパッケージングだったから花嫁の送迎にも活躍した。フロントには進歩的なウイッシュボーンの独立懸架を採用し、途中で加わった1900シリーズでは時代に先駆けてオーバードライブ付き3速MTも設定する。

2代目の登場は62年9月だ。トヨタのTの字をモチーフにしたフロントグリルに、4灯式ヘッドランプを組み合わせ、インテリアも水平基調の開放的なデザインとした。65年秋にM型直列6気筒エンジン搭載車を投入したのを機に、6気筒がプレミアムセダンのスタンダードとなる。また、高性能なツインキャブ仕様を加え、スポーツセダンの先陣を切った。ワイドボディに日本初のV型8気筒エンジンを積むクラウン・エイトも衝撃をもって迎えられている。

67年登場の3代目は高品質と優れた安全性を謳い文句に、白いボディカラーやクラス初の2ドアハードトップ(HT)を設定した。オーナーカーとしての色彩を強めるのは、この3代目からだ。
これに続く4代目(71年登場)は「クジラ」の愛称を持つデザイン史に残る意欲作で、カラードバンパーやフェンダー一体型のウインカーランプを採用している。最先端を行く電子制御自動変速機のEATや電子制御燃料噴射装置のEFIを採用したことも驚きだ。74年秋に登場した5代目は、安全性を高めるためにセンターピラーを残した4ドアピラードHTを設定し、世界初の4速ATも実用化する。6代目(79年登場)は、80年秋にターボや新世代直列6気筒エンジンを搭載した。

83年登場の7代目は「いつかはクラウン」のキャッチフレーズを使い、ハイソカー旋風を捲き起こしている。また、4輪独立懸架となった最初のクラウンでもあった。
最新のパワーステアリングやABSの先駆けとなる4輪ESC(電子制御アンチスキッドコントロール)など、電子デバイスを積極的に導入し、Sパッケージをベースにスポイラーを装着したスポーティな「アスリート」も特別仕様車として送り込んだ。このアスリートは、後にカタログモデルに昇格する。8代目(87年登場)は4ドアHTにワイドボディを設定し、V型8気筒も加わった。電子制御エアサスペンションやナビ機能を持つエレクトロマルチビジョン、統合制御の「ECT」 4速ATなど、今につながるハイテク技術も数多く盛り込んだ。

続く9代目(91年登場)では電子制御5速ATを設定し、新シリーズのマジェスタには初の4WDモデル、「i-Four」も投入する。10代目(95年登場)からはモノコック構造のボディを採用し、ビークル・スタビリティ・コントロール(VSC:車両安定制御システム)などの安全装備に加え、国際水準の衝突安全ボディや4WDシステムも採用した。21世紀を前に投入した11代目(99年登場)クラウンの注目は、エアロパーツを装着し、強化サスペンションや丸型リアランプを採用した「アスリート」だ。伝統の「ロイヤル」と並ぶ主役と位置付けている。また、2001年夏にはクラウン初のマイルドハイブリッドを追加した。

すべてを一新し、ゼロスタートとリセットしたのが2003年に登場した12代目だ。新世代プラットフォームにV型6気筒DOHCエンジンを搭載するなど、メカニズムを大きく変えたので「ゼロ・クラウン」と呼んでいる。13代目(2008年登場)はゼロ・クラウンを正常進化させ、アスリート系はさらにスポーツ感覚を強めた。この頃から環境性能の高いハイブリッド車を主役に据えるようになる。

14代目(2012年登場)は「CROWN ReBORN」を掲げ、フロントマスクを大胆に変えた。アスリート系は稲妻のような切れ込みのフロントマスクだ。主役を務めるハイブリッド車は、3.5LのV6から2.5Lの4気筒にダウンサイジングし、優れた燃費性能を実現した。先代の15代目(2018年登場)はオーナーの年齢層を引き下げるために若返りを図り、クーペ風のフォルムをまとっている。
日本の自動車市場で存在感を発揮し続けてきたプレミアムカーが、新しいステージに

さて前置きが長くなったが、日本が生んだ独創のプレミアムカー、エグゼクティブカーがクラウンだ。いつの時代も憧れの高級車であり、多くの人がオーナーになることを夢見てきた。歴代のクラウンは、独自の技術、純国産の技術にこだわり、高級車にふさわしい新技術を時代に先駆けて採用している。また、高級感と快適性に対するきめ細かな配慮、これもクラウンならではの伝統だ。

クラウンは、何度も大きな変革に挑んできた。最新の16代目クラウンも同様で、メカニズムだけでなくデザインも大胆に変えている。高級車の新しい基準を掲げ、世界に通用する走りも追求した。また、バリエーションを大幅に拡大し、クラウンスポーツでは進化させたハイブリッド車に加え、充電システムを搭載したPHEVの「RS」を投入する。

クロスオーバーに続く新世代のクラウンとして発表され、2023年11月に発売したのがクラウンスポーツである。第一弾のクロスオーバーより全長とホイールベースを切り詰め、サスペンションも専用にチューニングした。全長はクロスオーバーより210mm短く、ホイールベースも80mm短い2770mmだ。最初に2.5Lの直噴4気筒エンジンにモーターを組み合わせたトヨタハイブリッドシステム搭載の「Z」が発売された。これに続いて送り出されたのが、PHEVと呼ばれるプラグインハイブリッドの「RS」である。駆動方式は、どちらもリアをモーターで駆動する4WDのE-Fourだ。
待望のPHEV搭載の「RS」は魅力的な充電機能満載

追加された「RS」の最大の特徴は、充電システムを備えていることで、運転席側のリアサイドパネルに充電口を設けている。パネルを開くと充電ポートが現れるが、驚かされたのは200Vの普通充電だけでなく、日本の急速充電規格であるCHAdeMO(チャデモ)に対応させたことだ。トヨタは2代目のプリウスPHVで急速充電に対応させたが、コストダウンや急速充電でのEVユーザーとのモラル問題により、これ以降は普通充電だけに制限していた。だが、PHEVのバッテリー容量が増え、急速充電のインフラも整ってきたので、「RS」では急速充電にも対応できるようにしている。結果的にV2Hにも対応できるのでこれはうれしい改善だ。

普通充電は200Vだけではなく100Vの充電にも対応しており、充電時間は長くなるが、バッテリーの負担は軽減できる。ちなみに100V/6A(0.6kW)では空の状態から満充電まで約33時間だ。200V/30A(6kW)の普通充電器を使えば、満充電まで約3時間半で済む。最大出力50kW以上の急速充電器を使えば38分ほどで約80%まで充電できるのだから、時間を気にする人は便利と感じるだろう。外部給電できるV2H(Vehicle to Home=ヴィークル・トゥ・ホーム)機能も備えているから、蓄電池としても利用できる。災害時の自宅や避難所などで、非常用電源として機能させることも可能だ。

もう一つうれしいのは、収納バッグの中に車載充電ケーブルに加え、ヴィークルパワーコネクターも収めていることである。これを普通充電インレットに差し込めば100Vの外部給電用コンセントに早変わりするのだから、ありがたい。合計1500Wまで対応するので、消費電力の大きな電気製品を使うことも可能だ。ちなみにフロア下に18.1kWh、51Ahのリチウムイオン電池を搭載した。一充電でのEV航続距離は、実電費に近いWLTCモードで90kmだ。左側のリアフェンダー上にはガソリンの給油口があり、燃料タンク容量は55Lのたっぷりサイズ。無理なく1000kmをノンストップで走ることができ、上手に運転すれば1200km以上の距離を走れる計算だ。
モーター動力の存在感が増し、上質なパワーフィールを実現
クラウンは、3代目から高性能モデルを設定し、途中からは「アスリート」と名付けたスポーツモデルをラインアップに加えた。一時途切れたが、11代目でターボ搭載車とともに復活させている。アスリートの後継となる「RS」が登場するのは15代目のときだ。最新の16代目でもイメージリーダーは「RS」とした。ホイールベースを詰め、サスペンションも引き締めたクラウンスポーツのなかでも痛快な走りのPHEVに「RS」の称号を与えている。「アスリート」から続く栄光のネーミングに偽りはない。

クラウンスポーツRSのPHEVユニットは、RAV4やハリアーと基本的なメカニズムは同じだ。排気量2487ccのA25A-FXS型直列4気筒(直噴+ポート燃料噴射)DOHCエンジンのパワースペックは、ハイブリッド車のクラウンスポーツ「Z」より少しだけ低い。だが、フロントモーターは強力だ。システム最高出力は「Z」が172kW(234ps)であるのに対し、「RS」は225kW(306ps)とパワフルになっている。

実際に走らせてみると、その差は大きかった。最初はAUTO EV/ハイブリッドモードで走らせてみる。発進の一瞬だけはリアをモーター駆動して4WDになるが、その先は基本的に前輪駆動だ。街中や市街地を流れに乗って走るときは、モーターだけの上質なEV走行になる。アクセルを少し踏み込むと、瞬時にパワーとトルクが立ち上がり、滑らかな加速を披露した。静かで快適な運転を楽しむことができ、減速も上手だ。ノーマルモードからエコモードに切り替えると、鋭い瞬発力は少し削がれる。街乗り中心では十分な実力だ。

首都高のランプ進入ではモーターアシストの存在が際立ち、力強い走りを見せた。アクセルを少し強めに踏むだけで速い流れにも難なく乗ることができ、加速時も驚くほど静かだ。発進はモーター走行だが、アクセルを強めに踏み込んでいくとエンジンが目を覚ます。バッテリー容量が大きいから、モーター動力のアシストによる伸びのある気持ちいい加速を引き出すことが可能だ。

スポーツモードを選べば、さらにパンチの効いた、ダイレクト感覚の加速を引き出すことができる。ちょっとアクセルを踏み込んだだけでエンジンがアシストとして加わり、パワーとトルクが湧き出した。刺激的な加速を楽しみたいならスポーツモードがいいが、ノーマルモードは快適で、活躍の場が多い。低回転域ではエンジンの再始動が分かる場面もあったものの、加速時でも静粛性は高く、音の変化量も上手に抑え込んでいた。ただし、高速走行では路面からのロードノイズや風切り音が耳障りだ。逆に言えば、それほど静かで快適なクルマなのである。
車名にふさわしい驚異的に高いスポーツ性能
サスペンションはストラットとマルチリンクの組み合わせで、減衰力可変式のAVS(アダプティブ・バリアブル・サスペンション)を装備する。後輪操舵のDRS(ダイナミック・リヤ・ステアリング)とリアモーター駆動の4WDシステム(E-Four)の採用もあり、軽やかな操舵フィールと優れた路面追従性を披露した。AVSサスペンションの採用も見逃せない。連続するコーナーを走っても安定感があり、不快な揺れやフリクションも上手に抑え込んでいた。

リアシートに大事な人を乗せる機会が多いから、歴代のクラウンは乗り心地のよさを売りのひとつにしている。だが、この「RS」のサスペンションはちょっと引き締まった味付けだ。路面によっては硬さを感じた。スポーツモードを選ぶと、さらにハードになり、同時にステアリングの操舵フィールも手応えを増す。ハンドリングはスポーツカーのようにクイックだ。タイトコーナーでも身のこなしは軽やかで、狙ったラインに無理なく乗せることができる。リアは後輪操舵のDRSで逆位相にして旋回力を高めた。自慢のE-Fourも、アクセルを踏み込むとモーターが巧みにリアにトラクションをかけ、路面を舐めるように駆け抜けていく。これは新しいスポーツ感覚だ。

直進安定性は高いレベルにある。電動パワーステアリングの据わりがいいだけでなく、そこから切り出したときや戻したときの操舵感など、一連の動きはとても滑らかだ。ブレーキシステムも高性能パワートレインに見合ったものだった。コントロールしやすく、最後の利きもいいから安心できる。また、高速道路では追従クルーズの賢さにも驚かされた。前走車との距離の保ち方、減速に加え、カーブの大きさによる速度調節も絶妙だ。
目を引くアスリート系ボディとクラウンらしいインテリア

エクステリアは筋肉質のアスリート系ボディで、遠くからでもクラウンスポーツとわかる。ホイールベースを短くし、前後のオーバーハングも切り詰めるとともにワイドボディだからマッシブな印象が強い。前進感の強いクラウチングスタイルで、フェンダーまわりのボリューム感もダイナミックである。グリルを独立させたスポーティなフロントマスクやトレンドを押さえてクーペ風に処理したリアビューなども新鮮だ。最初に登場したクロスオーバーより若々しい。トヨタエンブレムを付けるクルマが多いが、クラウンは伝統の王冠エンブレムを誇らしげに付けている。これもオーナーにはうれしい配慮と言えるだろう。

足もとは235/45R21サイズのミシュラン製eプライマシーと専用のマットブラック塗装を施した8.5Jのワイドな10本スポークアルミホイールで踏ん張り感を上手に演出した。eプライマシーはEVのために開発された最新のエコタイヤだ。スポークの隙間からは、対向6ポットのキャリパーを備えた大径の真っ赤なブレーキシステムが顔を覗かせる。この演出も粋だ。

エクステリアと比べると、インテリアはおとなしい。クラウン伝統の水平基調のダッシュボードは、基本的にクロスオーバーと同じだ。ドライバー側と助手席側を非対称デザインとし、助手席側は囲まれ感を強調した。クロスオーバーより質感は向上し、配色にも工夫を凝らしている。試乗した「RS」は、センターコンソールや助手席側のドアトリムにレッドの表皮を大胆に使った、ブラック&センシュアルレッドの専用インテリアだった。シートベルトも赤地とし、トータルコーディネートしている。また、本革巻きステアリングにはパドルシフトを装備し、6時の位置には赤い挿し色を加えた。アクセルペダルは、踏力コントロールをしやすいオルガン式だ。

この「RS」は、フロントにホールド性に優れ、ショルダー部にも厚みを持たせた専用のスポーツシートが用意されている。身体にフィットし、パワー機構が標準だから最適なドライビングポジションを取りやすかった。リアの空間は取り立てて広いわけではないが、適度なタイト感がスポーティな味わいを演出している。ラゲッジルームも平凡な広さだ。

いくつか気になる点はあるもののクルマとしての完成度はかなり高い。販売価格は750万円を超えているが、PHEVは補助金もそれなりに出るから「Z」との出費の差はグッと詰まる。プレミアムスポーツとしての実力が高いなど、かなり魅力的だ。長い歴史を誇るクラウンのなかでも、もっとも異色といえる一台は、若い人から歴代のクラウンを乗り継いできたベテランまで、幅広い年代の人が長く付き合っていけるだろう。
撮影:宮越孝政
〈スペック〉
TOYOTA CROWN SPORT RS
| 全長×全幅×全高 | 4720mm×1880mm×1570mm |
| ホイールベース | 2770mm |
| 車両重量 | 2030kg |
| 乗車定員 | 5名 |
| エンジン | A25A-FXS型直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 2487cc |
| 最高出力 | 130kW(177ps)/6000rpm |
| 最大トルク | 219Nm(22.3kgf-m)/3600rpm |
| モーター種類 | 前後 交流同期電動機 |
| モーター最高出力 | 前134kW(182ps)/後40kW(54ps) |
| モーター最大トルク | 前270Nm(27.5kgf-m)/後121Nm(12.3kgf-m) |
| システム最高出力 | 225kW(306ps) |
| バッテリー容量 | リチウムイオン電池 51Ah(18.1kWh) |
| EV走行換算距離(等価EVレンジ) | 90km(WLTCモード) |
| ハイブリッド燃費 | 20.3km(WLTCモード) |
| 駆動方式 | 後モーター駆動の電気式4WD(E-Four) |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| サスペンション | 前 ストラット、後 マルチリンク |
| タイヤサイズ | 235/45R21 |
| 税込車両価格 | 765万円 |
※本記事の内容は公開日時点での情報となります
〈ギャラリー〉













この記事の監修者

片岡 英明
1954年、茨城県生まれ。自動車専門誌で編集に携わった後、独立してフリーのジャーナリストに。新車のほか、クラシックカーやEVなどの次世代の乗り物にも興味旺盛で、イベント参加することも多い。AJAJ(日本自動車ジャーナリスト協会)会員。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。