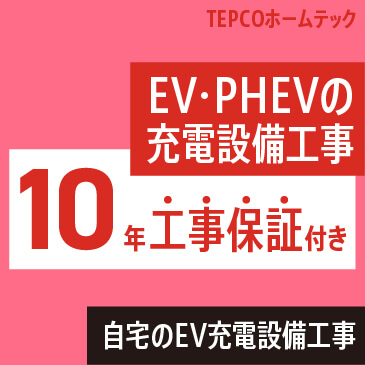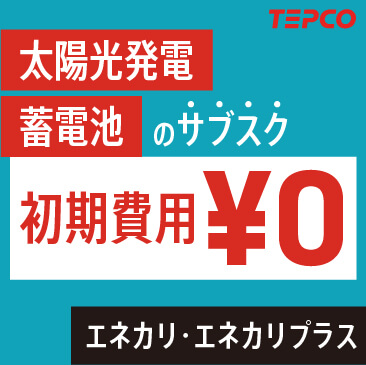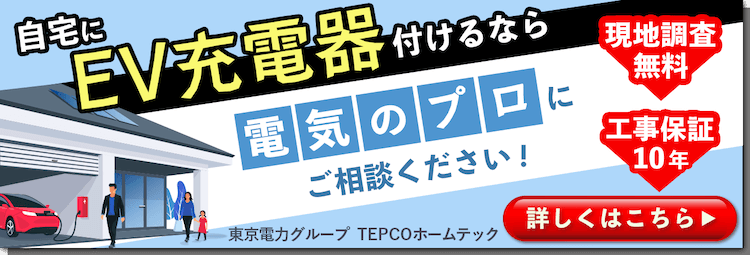【連載:EVのウソ・ホントVol.3】電気自動車(EV)にまつわる噂話を検証していく本連載。第3回目のテーマは、EVの電欠時の対処についてです。EVは駆動用バッテリーの充電が切れて電欠になると「レッカー車でけん引できない」というのですが、これは本当なのでしょうか。JAFに情報の真偽について聞いてみました。
メディアが指摘する「EVはけん引できない」説

EVユーザーのなかには長期休みにドライブ旅行に出かける人もいることでしょう。EVで遠出をするなら、注意しなければいけないのはやはり電欠(駆動用バッテリーの充電切れ)です。
夏休みや大型連休の時期は、高速道路のサービスエリア(SA)などに設置された急速充電器がフル稼働するので充電渋滞が発生しがちです。余裕をもった充電計画を立てておかないと、目的地に向かう途中にまさかの電欠となり、立ち往生することになりかねません。そうなったらロードサービスに救援を依頼することになります。
2000万人以上のドライバーが会員となっているJAF(日本自動車連盟)のロードサービス救援データによると、2023年4月から2024年3月までの1年間に実施されたEVのロードサービスは8625件あり、このうち電欠は975件で、全体の約11%を占めています1)。

このEVの電欠について気になる話があります。それは「EVは電欠になるとレッカー車でけん引できない」という噂です。
ガソリン車がガス欠になった場合、ロードサービスを呼べば一定量の燃料を補給してもらえますし、車が動かなくなった場合でもレッカー車でディーラーや修理工場までけん引してもらうことが可能です。ところが、電欠したEVはけん引できないというのです。この話は以前から自動車メディアなどに指摘されており、実際に「EVは電欠したとき、けん引できない」「EVは充電が切れると人力で動かせない」などと報じるメディアもあります。
たしかに、その場で給油することができるガソリン車のガス欠と違い、EVの充電には時間がかかるので、電欠になると現場での応急対応がむずかしい面もあるでしょう。とはいえ、「電欠になるとけん引できない」ということがありえるのでしょうか。
【あわせて読みたい記事】
▶EVロングドライブ、充電計画はどう立てる?熟練経験者に聞いた!
噂の根拠はEVが搭載するモーターの特性!?

真偽を確かめる前に、まずけん引の種類を整理しておきます。ひと口にけん引といっても、故障車などをけん引するには大きく分けて「ロープなどでけん引する」「前輪か後輪、または四輪を持ち上げてけん引する」という2つの方法があります。
ロープけん引は、ベルトやワイヤーで車と車を接続してけん引する方法で、ロードサービスを利用せずに知人や友人などの車でけん引するケースもあるでしょう。一方、JAFなどのロードサービスではレッカー装置で前輪か後輪を持ち上げ、車種によっては四輪すべてを持ち上げてけん引します。車積載車に積み込んで移動させる場合もあります。いずれもベテランドライバーなら一度は経験したことがあるかもしれません。

なお、多くのEVは取扱説明書にけん引時の注意事項が書いてあります。日産「リーフ」の取扱説明書には「前輪または4輪を持ち上げてけん引してください」などの注意事項が箇条書きされているほか2)、トヨタ「bZ4X」の場合、けん引はディーラーや専門業者への依頼を推奨することや、レッカー車でけん引するときの方法がFWD車、4WD車ごとに図を交えて説明されています3)。
取扱説明書に前輪などを持ち上げてけん引するよう書かれてあったり、駆動方式ごとに異なるけん引方法が書かれてあったりするのは、EVが搭載するモーターの仕組みが関係しています。
EVの動力源のモーターは電気をエネルギーにして回転しますが、外部からの力でモーターを回すことで発電もします。この特性を利用した電動車特有の仕組みが回生ブレーキです。つまり、EVをけん引するときに駆動輪が地面に接していると、モーターが回って発電し、システムにダメージを与えるおそれがあるわけです。
こうしたEVの特性が「EVは電欠になるとけん引できない」説の根拠になっている可能性があります。逆にいうと、電欠時は駆動輪を持ち上げてけん引すれば問題ないということにもなるかもしれません。はたして「EVは電欠になるとけん引できない」説の真偽はどうなのでしょうか。JAFにズバリ聞いてみました。
【あわせて読みたい記事】
▶【図解】回生ブレーキとは?減速や発電の仕組みからEV車種別の操作までを解説
「けん引できない」説に対するJAFの見解は?

話を聞いたのはJAF東京支部ロードサービス隊のベテラン、管理主管の松本暁典さんです。さっそく「EVは電欠になるとけん引できないという噂があるのですが、本当ですか?」と質問してみました。それに対する松本さんの回答が以下のコメントです。
■松本さん(JAFロードサービス隊)のコメント
電欠していても、駆動輪を持ち上げれば問題なくけん引できます。基本的にFWDなら前輪を、RWDなら後輪を持ち上げてレッカー車でけん引し、近くのディーラーなどの充電スポットまで搬送いたします。ただし、幹線道路ではRWD車だからといって車両を後ろ向きに動かすことはできません。また、EVはパーキングブレーキが電動化されていることが多く、電子制御されたパーキングブレーキを完全に解除することができない場合があります。それらを総合的に考慮して、最近は四輪すべてを持ち上げてレッカー車でけん引するケースが増えています。

やはり駆動輪を持ち上げれば電欠したEVもけん引することができるようです。しかも、松本さんによると、場合によっては駆動輪が接地した状態でロープけん引することもあるといいます。
■松本さん(JAFロードサービス隊)のコメント
電欠した車両が狭い路地に停車しているなど、レッカー車でけん引するのがむずかしいケースがあります。そういう場合はレッカー移動が可能な広い場所までいったんロープでけん引します。EVのけん引は車両を損傷しないように駆動輪を持ち上げるのが基本ですが、やむをえず駆動輪が接地した状態でけん引する場合は、取扱説明書の指示に従って作業します。
たしかに日産「リーフ」の取扱説明書を見ると、「やむをえず4輪接地の状態でけん引されるときは、シフトポジションをNにした状態で行ってください」、「速度30km/h以下でできる限り短距離の移動のみとしてください」と書かれてています2)。駆動輪が接地している状態でけん引するのは絶対にNGというわけではなく、車種や条件、けん引する速度・距離にもよるのでしょう。
さらに、JAFではバン型のロードサービスカーに充電可能な機材を搭載した「EV充電対応サービスカー」の導入も検討しているといいます4)。現在は一部地域で試験運用している段階ですが、将来的にはガス欠と同様に、電欠時に応急的な急速充電をすることにより、自力で充電スポットまで移動できるようになるかもしれません。
【あわせて読みたい記事】
▶電気自動車もバッテリー上がりを起こす?専門家が教える判断方法や解決策
EVの電欠を避けるために注意すべきポイント

電欠になってもレッカー車でけん引できることがわかってひと安心ですが、一番いいのは「そもそも電欠にならないこと」です。そのためには、日ごろから以下について気をつけましょう。
ひとつは「航続可能距離表示を信用しすぎない」ことです。航続可能距離表示とは、現在の駆動用バッテリーの残量で走行できるおおよその距離のこと。あくまで「おおよそ」の航続可能距離ですから、道路の高低差やエアコンの稼働状況、道路の混み具合によっては、実際に走行できる距離とは乖離がある場合があります。
また、「出力制限警告表示が点灯したら無理して走り続けない」こともポイントです。出力制限警告表示はまもなくバッテリー切れを起こすサインですから、電欠になって立ち往生する前に安全な場所に停車し、すぐにロードサービスに連絡しましょう。
その際に自分の車がEVであることや駆動方式をロードサービスに伝えておくと後の作業がスムーズになります。さらに、ロードサービスカーが到着するまでの間、「EVのパワースイッチを必ずオフにしておく」こともとても重要です。
■松本さん(JAFロードサービス隊)のコメント
駆動用バッテリーの充電が切れるのはガソリン車におけるガス欠と同じ状態ですので、シフトポジションをニュートラルに入れることができれば人力で押すことも可能です。しかし、電装品などをつけっぱなしにして12Vバッテリーが上がってしまうと、シフトポジションが自動的にパーキングに入ってしまい、動かすこともできなくなります。そうなったらご自身の安全を確保したうえでロードサービスを要請いただければと思います。
12Vバッテリーとは、電装品向けの補機類用バッテリーのことです。EVは高圧の駆動用バッテリーを搭載していますが、電装品はガソリン車と同様に12Ⅴのバッテリーで動かします。12Vバッテリーが上がってもサービスカーとケーブルで接続して復旧することは基本可能です。
ただし、以上のことはあくまで万が一の話です。EVを正しく運用していれば、電欠はそうそう起こるものではありません。くれぐれも安全に注意し、EVで出かける長期休みを楽しんでください。
※本記事の内容は公開日時点での情報となります