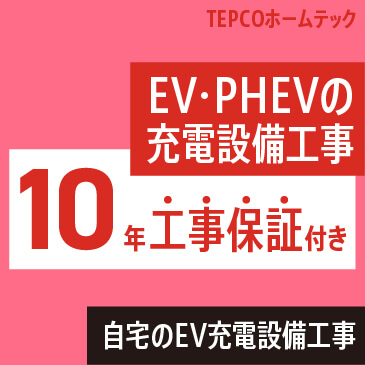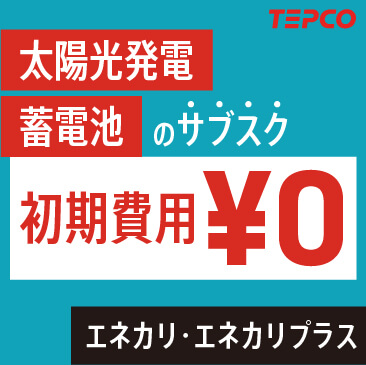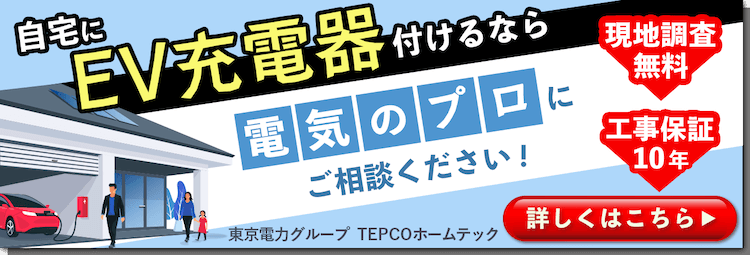電気自動車(EV)とエンジン車で全く違うのが「充電」です。公共の充電スタンドが全国に設置されているのをご存じの方は多いでしょうが、実際に充電スタンドを使いこなすには、最低限の基礎知識を理解しておくことが大切です。充電スタンドにはどんな種類があり、どう使うのか。また、充電スタンドの探し方などをご紹介します。
- 外出時に利用できる充電スタンドの種類
- 充電スタンドはどこにある? 設置場所を探すには?
- 充電カードの基礎知識と料金相場
- 充電スタンドの利用方法(手順、支払い方)
- 自宅に充電設備を導入するための設置費用
- 充電スタンドは「みんなで使うインフラ」
注:本記事で「EV」と表現する場合、「BEV(Battery Electric Vehicle)」を意味しています。ハイブリット車(HV)、プラグインハイブリッド車(PHV・PHEV)や燃料電池自動車(FCV)とは区別しています。
外出時に利用できる充電スタンドの種類

電気自動車(EV)の充電には、自宅ガレージなどで行う「家充電」と、外出先で行う「外充電」があります。充電スタンドは「外充電」のときに利用することになります。
〈図〉EVの充電の分類

外充電のなかには「急速充電」と「普通充電」があります。現在、日本で市販されているEVのほとんどには、2つの充電口が装備されています。大きいほうが急速充電用の充電口で、小さいほうが普通充電用の充電口と覚えておきましょう。
ただし、外部充電が可能なプラグインハイブリッド車(PHV・PHEV)において、ほとんどの輸入車(メルセデス ベンツA250e以外)は現在のところ普通充電のみの対応で、急速充電用の充電口はありません。
では、急速充電と普通充電は何がどう違うのか。ポイントを説明しておきます。
普通充電とは?

普通充電は交流の電源で行います。自宅ガレージの充電用200Vコンセントや「普通充電器」と呼ばれる充電器を使うのが一般的です。普通充電器自体は、自宅に設置することが可能なほか、自宅外に設置されている公共の充電用スタンドとして利用されています。
急速充電との大きな違いは充電速度、言い換えると「充電器の出力」です。日本国内の普通充電用充電スタンドの多くが、3kW(200V×15A)の出力で充電する仕様になっています。つまり、1時間で充電できる電力量は「3kWh」です。
10時間充電した場合、電力量は30kWhとなります。たとえば、62kWhの日産リーフe+を残量がゼロに近い状態から満充電にするためには、約20時間が必要という計算になります。

最近は、EVのバッテリーが大容量化する傾向にあり、テスラ専用の『デスティネーションチャージャー』をはじめ、6kW以上の出力をもつ普通充電器が増えてきています。
ただし、6kW以上の高出力型の普通充電器は、車種によって対応していないケースがあるので、もし、高出力型の普通充電器を自宅に設置したいと思った場合には、事前にディーラーなどで確認してください。
また、6kWの出力を得るためには、200Vの場合は30A(6kW ÷ 200V)、100Vに換算すると60A(6kW÷ 100V)という電流が必要です。一般的な家庭の電力契約で60A(100V)という大きな電流を確保するためには、契約容量の見直しなどが必要です。必ず、業者などに相談して、設置場所や電力会社との契約容量などを確認するようにしてください。
急速充電とは?

画像:iStock.com/jamesteohart
急速充電とは、文字通り、普通充電に比べて高出力で短時間に充電する方法です。前述のように車両側の充電口も普通充電とは異なり、急速充電器からEVへの電気は直流を使用します。
急速充電器はおもに高速道路のSAやPA、幹線道路沿いの道の駅、ディーラーなどに多く設置されています(個人の自宅に急速充電器を設置することは困難です)。また、多くの急速充電器の利用は1回30分と決められています。
出力は充電器によって異なりますが、現状の日本国内に設置されている急速充電器はおおむね20~50kWとなっており、今後、90kW以上の高出力器の設置が進められる計画になっています1)。
先に説明した普通充電の出力は3~6kW程度ですから、20~50kWの急速充電器が高出力であることがわかります。とはいえ、たとえば、出力50kWの急速充電器で30分間充電しても、補給できる電力量は最大で25kWhという計算になります。62kWhの日産リーフe+では、1回の急速充電で回復できる電力量は最大でも約40%程度ということです。

また、高出力での急速充電時には車両と充電器が通信によって情報を交換し、電力(電流値)を制御しています。これは、EVの車種によって急速充電で受入可能な最大電力に制限があることを意味しています。
また、多くのEVが搭載しているリチウムイオンバッテリーには、満充電に近づいていくと急速充電の受入電力を抑える特性があります。
普通充電と急速充電の使いこなし方

時間をかけて、状況によっては満充電を目指すのが普通充電。電力を素速く注ぎ足して、必要な分を充電するのが急速充電。同じ充電でも、普通充電と急速充電は目的や使い方が異なるのです。
EVやPHVなどの外部から充電可能な電動車(プラグイン車)でロングドライブを行う際は、事前にルート上で急速充電できる充電スタンドを確認して、余裕をもって走りきるための充電計画を立てておくのがおすすめです。
また、宿泊施設やレジャー施設などを利用するのであれば、その駐車場に充電設備があるかどうか、また、近くで充電できる場所があるかどうかも確認しておきましょう。長時間滞在する宿泊施設などでは、30分制限がある急速充電器より、さほど時間を気にせず満充電まで充電できる普通充電器を利用するのがむしろ便利です。
これからプラグイン車が普及してくるほどに、普通充電設備を備えているかどうかが、宿泊施設やレジャー施設を選ぶ重要なポイントになってくることでしょう。
〈表〉普通充電・急速充電を使いこなすためのポイント
• 普通充電、急速充電の役割を理解する
• ドライブ時には、充電計画を立てておく
• 宿泊・レジャー時には、宿泊先・付近に充電設備があるか確認しておく
充電スタンドはどこにある? 設置場所を探すには?

資源エネルギー庁の集計によると、2020年の給油所(ガソリンスタンド 等)数は約3万カ所2)で年々減少しております。これに対し公共の場所にある充電スポットは、ガソリンスタンドの約6割に上る1万7740カ所となっています(2021年2月時点ゼンリン調べ)。 プラグイン車の増加に伴い、充電スポットの整備はこれからも進んでいくことでしょう。
また、テスラやポルシェなど一部のメーカーでは自社のEVユーザーのために独自の充電スタンドを設置しています。
とはいえ、自分自身がEVやPHVに乗っていないと「いったいどこにそんな多くの充電スタンドがあるの?」と感じる人もいることでしょう。充電スタンドはどんな場所に設置されているのか。また、プラグイン車で出かけるとき、充電スタンドを効率よく探す方法などについて解説します。
充電スタンドが設置されている場所の傾向

前述のように、普通充電と急速充電は目的や使い方が異なります。従って、充電スタンドとして設置されている場所も、普通充電器と急速充電器で異なる傾向があります。
〈表〉充電スタンドが設置されている主な場所
| 充電器の種類 | 主な設置場所 |
| 普通充電器 | 宿泊施設、商業施設、オフィスビルの駐車場、カーディーラー |
| 急速充電器 | 高速道路のSAやPA、幹線道路沿いの道の駅、コンビニの駐車場、地方自治体の施設、カーディーラー、商業施設 |
普通充電器の充電スタンドが設置されている場所
まず、普通充電器は、滞在時間が長い宿泊施設や商業施設、オフィスビルの駐車場などに設置されるケースが多くなっています。最近は、たとえば東京都港区の六本木ヒルズ(239基)3)や、東京ミッドタウン(125基)4)のように、多くの駐車区画に普通充電器を設置して、電力の状況などに応じて順次充電していく仕組みを導入するような事例も増えています。
また、宿泊客が利用できるEV用の200Vコンセントを備えていたり、普通充電器を設置する宿泊施設も増えてきています。たとえば、長野県白馬村では30軒ほどの宿泊施設5)に設置されています。
急速充電器の充電スタンドが設置されている場所
長距離ドライブの途中で注ぎ足し等の充電を行う急速充電器は、高速道路のSAやPA、幹線道路沿いの道の駅に多く設置されています。ファミリーマート(全国で700店舗程度)6)やローソン(全国で200店舗程度)7)などのコンビニエンスストアの駐車場にも多く設置されています。また、役場や公園など地方自治体の施設などに設置されているケースもあります。
また、早くからEVを発売した日産や三菱などのカーディーラーや、イオン(全国で200店舗程度)8)など全国チェーンの商業施設にも設置されています。こうした施設では、普通充電器と急速充電器の両方の充電スタンドが多い傾向があります。
ことにカーディーラーの急速充電器は、自宅ガレージで充電できないユーザーが日常的な充電に利用することも想定しています。もちろん、ルールに従ってディーラーや商業施設の急速充電を、通りすがりの経路充電で使用するのは問題ありませんが、今後、プラグイン車が増えてくるにつれ、各地の充電スタンドが混雑することも想定されます。普通充電と急速充電の違いを理解して、マナーを守って活用しましょう。
どこで充電できる? 目印は『CHARGING POINT』マーク

充電スタンドの目印として道路標識のように掲示されているのが『CHARGING POINT』マークです。普通充電器と急速充電器の充電スタンドは区別して活用する必要があるので、『CHARGING POINT』マークも設置されている充電器の種類で異なります。
普通充電器のマークの特徴
〈図〉普通充電起用案内サイン

EVを模したアイコンの下に『CHARGING POINT』と記されているのは同じですが、普通充電器の場合は上部に「EV100V」もしくは「EV200V」と記されています。これは、設置されている普通充電器(もしくはコンセント)が100Vか200Vかを示しています。
とはいえ、EVに搭載されているバッテリーは大容量なので、100Vでの充電には単純計算で200Vの倍の時間がかかってしまうこともあり、充電スタンドに設置されている普通充電器は200Vであることがほとんどです。
なお、100Vコンセントからの普通充電には200Vとは別の充電ケーブルが必要であり、市販EVの多くは100V用の充電ケーブルを標準装備されていません。
急速充電器のマークの特徴
〈図〉急速充電器用案内サイン

標識の上部に「EV QUICK」と記されているのが、急速充電器の目印です。日本国内に設置されているCHAdeMO(チャデモ)規格の急速充電器には20~50kW程度と出力に幅がありますが、マークではその場所に設置されている急速充電器の出力まではわかりません。
充電器設置場所の目印のひとつが『CHARGING POINT』マーク
『CHARGING POINT』マークは、日本国内の公共充電スタンドの多くに掲示されています。このマークは東京電力が商標登録しています。
しかしながら、このほかにも自治体等の独自のデザインのマークが設置されいる場合もあります。
【あわせて読みたい記事】
▶CHAdeMO(チャデモ)とは?EVの急速充電器規格の基礎知識や最新事情を解説
充電スタンドの場所を探せるサービス

実際にプラグイン車で充電スタンドを利用する際には、あらかじめルート上の充電スタンドの場所を確認して充電計画を立てておくのがスムーズです。市販されているEVやPHVの多くは、ナビゲーションシステムを活用して充電スタンドを探せる機能を備えているので、ドライブ途中などではそうした機能を活用することができます。
とはいえ、車載のシステムは車内でしか使えないので、ドライブ前夜にあらかじめ調べて計画を立てておきたいといった際には不便です。また、充電スタンドは新設されたり廃止されたりすることがあります。
こういった時、最新情報を知り、ドライブ計画を立てるために便利なのが、ウェブサイトやスマホアプリの充電スタンド検索サービスです。
充電スタンドを探せるサービス①「e-Mobility Power」公式サイト

まず、日本全国の公共充電スタンドを網羅する東京電力グループのe-Mobility Power(eMP)が、公式ウェブサイト上で提供しているのが、『充電スポットMAP』です。
充電インフラネットワークであるe-Mobility Powerネットワーク(eMPネットワーク)に加盟、もしくは提携している充電スタンドを、「急速のみ」「普通のみ」「急速+普通」を示すアイコンで地図上に表示してくれます。また「充電スポット一覧」や「充電スポット運休のご案内」といった情報も提供されています。
▼e-Mobility Power「充電スポットMAP」

ウェブサイト:https://usr.evcharger-net.com/rcs/map/web/pc?id=eb7ceba1e46ea98f06cfa8b9b0ce0c1e
運営元:株式会社e-Mobility Power
充電スタンドを探せるサービス②民間サービス
eMPネットワークだけでなく、独自設置を含めて全ての充電スタンドを検索できる民間サービスのウェブサイトやスマホアプリもあります。代表的なサービスをピックアップしておきます。
どちらのサービスも、ウェブサイトとスマホアプリの両方で情報提供を行っています。新設や故障、休止などの情報もおおむね迅速に反映されて、利用者の口コミ情報などを得られるのもこうしたサービスの便利さになっています。
さらに、たとえば『EVsmart』は、出発地と目的地、車種などを入力すると自動的に充電計画を提案してくれる『経路検索』の機能も備えるなど、それぞれプラグイン車ユーザーの利便性を考えたサービスが提供されています。
また、こうした民間サービスと連携しつつ、電動車を発売する自動車メーカーの多くが自社ユーザーに向けたスマホアプリやカーナビ情報などを提供しています。
高速道路上の充電スタンドを探せるサービス
さらに、高速道路でロングドライブする際に、ルート上のSAやPAに設置された充電スタンドの場所を探せるのが、ジャパンチャージネットワーク(2021年6月1日にeMPが全株式取得)のスマホアプリ『高速充電なび』です。スマホアプリのみの提供で、路線・ルート・名称での充電スタンド検索や、充電器の満空情報、利用中の場合の充電開始時間、SAやPA内の配置などを知ることができます。
充電カードの基礎知識と料金相場

eMPネットワークの公共充電スタンドを利用するには、事前に登録した充電カードによる認証が必要です。また、普通充電器、急速充電器それぞれに設定された利用料金がかかります。充電カードや利用料金は、どういう仕組みになっているのでしょうか。
充電スタンド利用に必要な「充電カード」とは?

eMPネットワークに繋がっている充電スタンドを利用するには、普通充電、急速充電ともに「充電(認証)カード」が必要です。eMPネットワークの充電器は通信機能を備えていて、「充電カード」を充電器本体、または近くに設置されている認証機器のセンサーにかざすことで、事前にクレジットカード情報などを登録した利用者であることを確認し利用料金を課金します。
充電カードは、充電インフラ整備を担うeMPが発行する『e-Mobility Power カード(eMPカード)』の他に、プラグイン車を発売しているメーカーやJTBなどが、eMPネットワークと連携した独自の充電カードを発行しています。
自動車メーカーが発行する充電カードは、おおむね自社のプラグイン車ユーザーのみに発行されるものです。所有する車種に関わらず利用できるのは以下の3種類のカードです。
〈表〉所有する車種にかかわらず利用可能な充電カード
| 発行している会社 | カード名 |
| e-Mobility Power | e-Mobility Power カード |
| 日産 | ZESP3(ゼロ・エミッションサポートプログラム3)カード |
| JTB | おでかけCard |
マツダやプジョー(グループPSA)などは、EVやPHVを発売していますが、独自の充電カードは発行していません。そうしたメーカーのプラグイン車ユーザーが公共の充電スタンドを便利に使うためには、車種を問わずに利用できるカードからどれかを選んで事前に入会しておく必要があります。
充電スタンドの利用料金はいくらくらい?

各社の充電カードには、それぞれ「月会費」と、普通充電と急速充電それぞれの「都度料金」が設定されています。また、ほとんどのカードで発行時に発行手数料がかかります。
自動車メーカー発行の充電カードのなかで唯一、車種を問わずに入会可能な日産『ZESP3』カードは以下のような仕組みになっています。
〈表〉ZESP3の基本の料金体系(税込)
| プラン名 | プレミアム10 | プレミアム20 | プレミアム30 | シンプル |
| プランに含まれる 充電回数※1 |
急速充電10回 (100分相当) (普通充電無制限) |
急速充電20回 (200分相当) (普通充電無制限) |
急速充電40回 (400分相当) (普通充電無制限) |
設定なし |
| 月額基本料金 (3年定期契約料金) |
4400円 (2750円) |
6600円 (4950円) |
1万1000円 (9350円) |
550円 |
| 充電料金※2 (急速充電器) |
385円/10分 | 330円/10分 | 275円/10分 | 550円/10分 |
| 充電料金 (普通充電器) |
どれだけ使っても0円 | 1.65円/分※3 | ||
| 登録手数料 | 1650円/初回のみ | |||
※1 充電時間は10分/回。使わなかった回数は翌月に繰り越し
※2 プラン以上に使用する場合
※3 小数点以下の取り扱いによって実際の請求金額とは異なる場合があります
日産『ZESP3』の場合、毎月の急速充電器利用頻度に合わせてプランを選択する仕組みになっています。
このほか、各自動車メーカーが発行する充電カードは基本的に自社ユーザーへのサービスという面があり、入会時の発行手数料や、一定期間の月会費、都度利用料金が無料になるなどのメリットが設定されているケースが多くなっています。各社のカードは自社プラグイン車ユーザーに向けたものなので、詳しくは購入ディーラーなどで確認してください。
「充電カード」を持っていない場合の充電手段とは?
「充電カード」を持っていない場合には、充電器に掲示された手順に従って「ビジター(ゲスト)認証」を行うことで充電できます。
それぞれの充電器が繋がっているプロバイダのシステムによって認証方法が異なりますので、用意されたスマホサイトなどにアクセスし、クレジットカード番号など必要な情報を登録した上で、充電器を使うことになります。プロバイダごとに「ビジター(ゲスト)認証」の方法や手順が違うので、不慣れな方にはかなり面倒な作業であることは否めません。また、ビジター充電の場合「月会費」はありませんが、都度利用料金が充電カードで利用するのに比べてかなり高くなります。10)
レンタカーなどで一時的にEVやPHEVを利用するのではなく、マイカーとして所有するのであればあらかじめ充電カードを取得しておくのが「便利でおトク」といえます。
また、前述したテスラやポルシェのように独自の充電スタンドを展開しているメーカーでは、それぞれの認証&課金システムで運用しています。ただし、テスラやポルシェのEVであっても、eMPネットワークの充電スタンドを利用する場合は、eMPカードなどの充電カードが必要です。
充電スタンドの利用方法(手順、支払い方)

eMPネットワークの公共充電スタンドを利用する際の、基本的な手順や留意点をご紹介します。
充電スタンドの基本的な使い方
充電カードを使用する場合、おおむね以下の手順で充電を開始します。
【充電を開始する時の手順】
① 指定された充電スペースに駐車する。
② EV・PHVのメインスイッチをオフにする。
③ 充電口を開けて充電ケーブルのコネクターを挿す。
④ 充電器に示された方法に従って充電カードで認証する。
⑤ 充電スタートのボタン(機種によって異なる)を押す。





充電を開始する際の手順は、急速充電でも普通充電でも基本的に同じです。前述のように、それぞれ充電口が異なるので注意(形状が異なるので間違えて挿すことはできないですが)してください。
充電口へのコネクター挿入と、充電カードでの認証は、順序が逆の充電器もあります。あらかじめ、充電器に掲示された手順を確認しましょう。
【充電を終了する時の手順】
① 充電器に掲示された方法に従って「充電終了」ボタンを押す。
② コネクターを外し、ケーブルを元の位置に戻す。
③ 充電口をきちんと閉じる。
④ 充電スペースから車を移動する。




以上が、充電終了時の基本的な手順です。
充電の停止タイミングは、車種により異なり、満充電で停止する場合や30分など時間経過により 停止する場合があります。一般的に、充電中はトイレ休憩などで車から離れても問題はありませんが、急速充電器はプラグイン車ユーザーがみんなで使うインフラなので、充電器が停止しているのに充電スペースに車を放置しないよう注意しましょう。
急速充電は必ず30分行わなくてはいけないものでもありません。ほとんどの機種で時間や容量をあらかじめ設定することはできない(一部可能な機種もあります)ですが、たとえば「70%を超えたからもう十分」と思えば、途中で停止することはできます。30分経過する前に途中で急速充電を終了する際にも、充電カードによる認証が必要な機種もあります。途中終了の場合も、充電器に掲示された手順を必ず確認してから行いましょう。
一方、普通充電器の場合、とくに利用の制限時間はありません。満充電になると自動停止するのは急速充電器と同様ですが、たとえば宿泊施設の駐車場で真夜中に充電器が停止したからといって、すぐに車を充電スペースから移動するのは現実的ではありません。基本的に、普通充電器の場合は充電スタンド設置施設に滞在中は停めたままで問題ありません(施設独自のルールがある場合は従いましょう)。
充電スタンドを利用するときのマナー・注意点
最も大切なマナーは「公共の充電器はプラグイン車ユーザーがみんなで使うもの」であるのを意識することです。充電のコネクターやケーブルは、元の位置に丁寧に戻しておくのがマナーです。充電口の閉め忘れにも注意してください。
30分の急速充電を行っても電池残量が十分に回復しなかった場合、もう1度急速充電することは「おかわり充電」などと言われています。原則1回30分ですが、ロングドライブの途中では「おかわり」したくなる気持ちもわかります。ただし、次の利用者が来たらすぐに充電を終了して交替できるよう、車から離れず待機しておくのがおすすめです。
支払いの方法
利用料金は、充電カード作成時やビジター認証申込時に登録したクレジットカードに課金されます(一部、電子マネーに対応したシステムもあり)。eMPネットワークの充電器でカード認証やビジター認証する場合、現金での支払いはできません。テスラやポルシェのシステムでも、事前登録のクレジットカードに課金されるのは同様です。市役所などで独自に設置している充電スタンドで、充電カードが不要な場合には、1回500円などの利用料を担当者に現金で支払う仕組みになっているケースもあります。
自宅に充電設備を導入するための設置費用

自宅に充電スタンドを導入できる?
プラグイン車の充電には、自宅ガレージなどで行う「家充電」と、外出先で行う「外充電」があることは最初に説明しました。「家充電」のための充電設備としては、スタンドタイプをはじめ、コンセントタイプ、壁掛けタイプ、V2H機器などの種類があります。
一戸建てなどの場合、比較的安価に設置可能なコンセントタイプが多く導入されています。
ただし、充電器のデザインにこだわったり、6kW以上の高出力な普通充電器を設置したいような場合は、壁掛けタイプやスタンドタイプの充電スタンドを設置することも可能です。EVやPHVを家庭の電気と連携する「V2H」機器は、急速充電用の仕組みを使っているため6kW程度の高出力で充電可能なものがほとんどです。
スタンドタイプの充電設備を導入したいと考えた場合、下記の表のように他の充電設備よりもコストが高いことに注意しましょう。同じく高出力が可能な「V2H」機器の導入には補助金の制度もありますが、スタンドタイプなどその他の充電設備を個人宅に設置する場合については、国の補助金はありません(一部の地方自治体には補助制度があるケースもあります)。
〈表〉充電設備毎の自宅(一戸建て)への導入費用の目安
| 種類 | 導入費用の目安(工事費込み) | メリット | デメリット |
| コンセントタイプ | 10万円程度 | ・コストが低い ・設置が簡単 |
・デザイン性に乏しい |
| 壁掛けタイプ | 20万円〜 | ・デザイン性がよい ・充電時間が短縮できる機種もある |
・コストがやや高め |
| スタンドタイプ | 20万円〜 | ・デザイン性がよい ・複数台での共用も可能 |
・コストがやや高め |
| V2H機器 | 80万円〜 | ・車の充電を家でも使用できる ・充電時間が短縮できる |
・コストが高め |
【あわせて読みたい記事】
▶︎電気自動車の自宅充電は超おトク! 電気代・工事代の目安を解説
▶︎V2Hの補助金は上限いくら? 国や自治体の制度、注意点を解説
▶︎V2Hの設置費用はいくら? 機器代・工事費までマルッと解説!
マンション住まいでも充電設備を導入できる?
公共の充電スタンドと同様に、利用者の把握や課金などの仕組みが必要になってくるのが、マンションなど集合住宅の駐車場に住民用の充電スタンドを設置する場合です。
集合住宅の駐車場に充電設備を設置するには、賃貸の場合は「建物のオーナーの許可」、分譲の場合は「管理会社や管理組合の合意」が必要となります。初期費用の負担や課金方法をどうするかといった課題もあって、なかなかハードルが高いのが現状ではありますが、最近は独自の課金システムを備えた普通充電器などのバリエーションも増えつつあります。
「マンション住まいだから家充電は諦めないと……」とは考えず、まずは管理会社などの専門業者に相談するところから始めてみましょう。
【あわせて読みたい記事】
▶マンションに電気自動車の充電器を設置するには?手順と注意点を解説
充電スタンドは「みんなで使うインフラ」

eMPネットワークの充電スタンドはもちろん、独自に設置されている充電スタンドも含めて、公共の充電スタンドはEVやPHVのユーザーが「みんなで使うインフラ」です。最近は充電器を利用するプラグイン車が増えてきたので、高速道路のSAやPAなど利用者が多い充電スタンドでは充電待ちが発生することも少なくありません。
eMPネットワークの急速充電器は1回30分以内と決められておりますが、必ずしも30分間充電しなければいけないわけではありません。
EVでのロングドライブに慣れてくると、自分の車で、出力50kWの急速充電器を使った場合「15分でもこのくらい充電できる」とか「この電池残量なら目的地までは十分だな」といった判断ができるようになってきます。
たとえば「このSAでの充電はトイレに行って飲み物を買うだけの15分で切り上げよう」といったふうに、充電待ちの状況も加味しながら臨機応変に充電スタンドを使いこなせるようになると、EVでのロングドライブをより効率的に楽しめるようになるはずです。
日本でのEV普及はまだ始まったばかりです。充電スタンドはマナーを守り、賢く使いこなして、充実したEVライフを楽しみましょう!