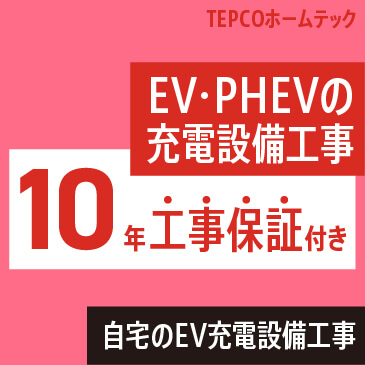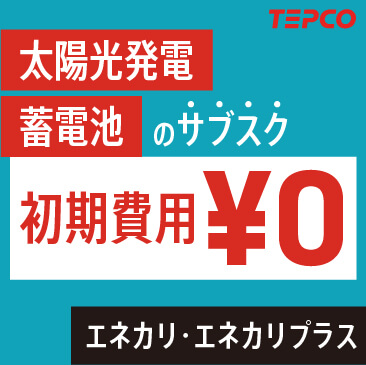車種が増えてきたとは言え、一般的に電気自動車(EV)の車両価格はガソリン車に比べて高いのが実情です。そのせいでEV導入に二の足を踏んでいる人もいることでしょう。しかし、EVの維持コストは充電方法などによって想像以上に低く抑えることができますし、補助金制度や減税措置があり、購入コストを抑えることも可能です。EVのメリット・デメリットについて、実際に利用して感じた意見を交えて解説します。
※この記事は2021年3月22日に公開した内容をアップデートしています。
注:本記事で「電気自動車(EV)」と表現する場合、「BEV(Battery Electric Vehicle)」を意味しており、PHEVやFCVとは区別しています。
EVとは? ガソリン車との違いとは?
はじめに、EVとガソリン車の最大の違いは、EVはエンジン=内燃機関を搭載していないことです。ガソリンなどの化石燃料はとても便利でパワフルなエネルギーですが、燃焼時に二酸化炭素(CO2)をはじめとする大気汚染物質を排出することが避けられません。
また、エンジンの中でガソリンが燃焼する際に、音や振動が発生します。しかし、EVのエンジンにあたる電気モーターの動きはスムーズで、ガソリン車と比較して走行時の静粛性が高く、振動が少ないという特徴があります。
こうしたそもそもの駆動方法の違いが、ガソリン車と比較した場合のメリット、そしてデメリットにも繋がっているのです。
【あわせて読みたい記事】
▶︎【図解】5分でわかる! 電気自動車(EV)の仕組み│どうやって動く? エンジン車との違いは?
EVの7つのメリット
ここからはEVに乗ることのメリットを考えてみます。実際にEVを所有し、使っている経験からお話しすると、EVに乗るメリットには大きく分けて次の7つがあります。
(メリット1)走行中の騒音や振動が少ない

まずEVに乗って感じるのは走行中の静かさです。モーターは「ヒューン」という音をわずかに発生するだけで、ガソリン車のような騒音はありません。さらに良いのは振動も少ないことです。音や振動が少ない車は疲れにくいです。遠方に出かけても意外なほど体の疲労が少ないのです。
力強い加速もEVの魅力です。ガソリン車は、エンジンの回転数をある程度上げないと加速できませんが、モーターは走り出した瞬間に最大の回転力(トルク)を発生するため、アクセルを少し踏むだけでスムーズ&滑らかに加速します。さらに踏み込めば、スポーツカーのような加速感を楽しむこともできます。
音が静かで振動が少なく加速も力強い、というのは、ガソリン車の場合は高級車の特徴でした。これらの要素をすべて備える電気自動車は、本質的に従来の高級車に近い車と言えるでしょう。
〈図〉EVオーナー192人へのアンケート調査

【あわせて読みたい連載】オーナーの感想を知りたい人、必見!
▶︎EV REAL LIFE 〜EVオーナーに直撃インタビュー〜
(メリット2)ガソリン車より走行コストが低い

走行コストの低さもEVの大きなメリットです。自宅での普通充電(家充電)をメインに利用すれば、ガソリン代よりも電気代のほうが圧倒的に安くなります。ざっと試算したところ、その差は倍以上。燃費の悪いガソリン車からの乗り換えなど条件次第では、3倍以上の差となるでしょう。
また、家充電は、「給油のためにガソリンスタンドに行く」という手間も省いてくれます。頻繁に給油していた人はこうした点もメリットに感じられるはずです。
(メリット3)災害時の電源として使える

EVは「走る蓄電池」とも言われていて、容量が非常に大きいバッテリーを搭載しています。たとえば、一般家庭の消費電力量が1日平均で10kWhとした場合、バッテリー容量40kWhの日産リーフなら、家庭で使う電力量の4日分もの電力量を蓄えられるバッテリーを搭載しているのです。住宅に設置される定置型の蓄電池の容量が多くても10kWh程度であることを考えると、その大きさがおわかりいただけると思います。
この大容量バッテリーは、非常時の電源として活用することができます。EVから電気を取り出す給電用機器があれば、家電などと直接繋ぐことが可能です。また、「V2H(Vehicle to Home)」と呼ばれる充放電機器を自宅に設置すれば、万が一停電が起きたとしても、自分が所有するEVを電源として、家庭内の電化製品が使えるようになるのです。
(メリット4)メンテナンスのコストが低い

あまり知られていないことですが、EVはガソリン車よりもメンテナンスコストを低く抑えることができます。
エンジンを搭載していないため、当然ながらエンジンオイルの交換は必要なく、回生ブレーキが多用されることで、ブレーキパッドの消耗も少なく抑えられます。
オイル交換が不要なら、交換したオイルを廃棄物として処理する必要もありません。また、ブレーキが減りにくいというのは、粉塵の発生を減らせるということです。メンテナンスの手間やコストが省けるだけでなく、こうした面でもEVは環境にやさしいと言えます。
(メリット5)「エネルギー意識」が高まる
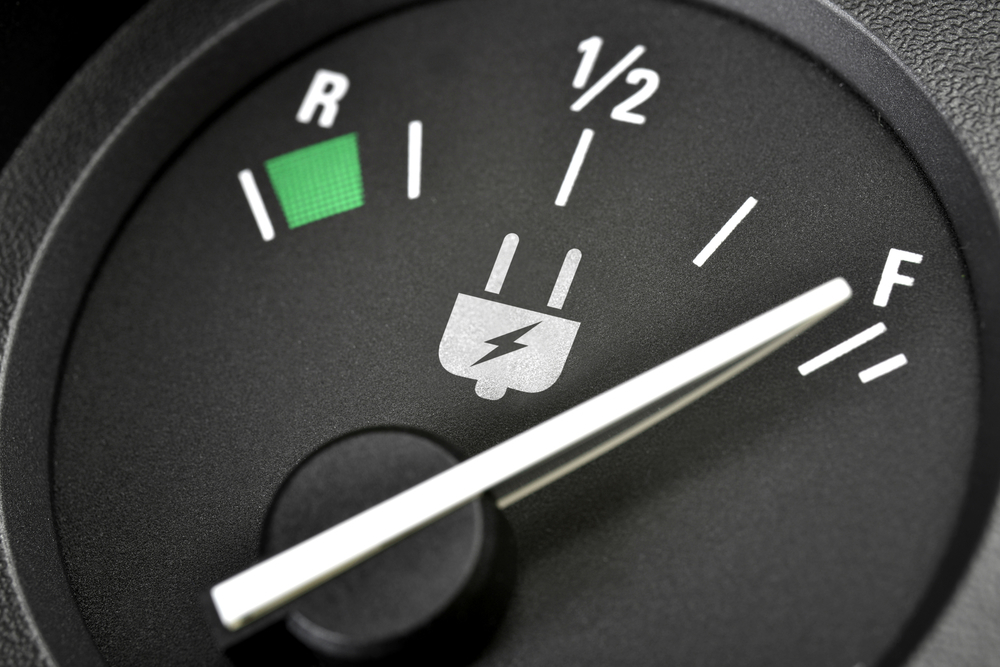
EVに乗っていると自然と「エネルギー意識」が高まります。
充電ひとつ取ってみても、「深夜の電気代が安いのはなぜか」「この電気はどのように作られたのか」と考えるようになります。
また、EVはガソリン車以上に走り方で燃費(電費:エネルギー消費)が変化します。急加速を繰り返せば、たちまちバッテリー残量が少なくなり、エアコンのオン・オフによっても残りの電力量で走れる距離が変わるのです。
「回生ブレーキ」もエネルギーを意識させてくれる機能のひとつでしょう。回生ブレーキとは、減速する際のエネルギーでモーターを発電機として使いバッテリーに充電する、EVならではのシステムのこと。つまり、長い坂道を下ると、走るほどにバッテリー残量が増えていきます。これは、エンジン車では体験できない感覚です。日産「リーフ(60kWh)」で富士山の五合目から麓まで下った際に、回生ブレーキによってバッテリー残量が約8%も回復したことがありました。
【あわせて読みたい記事】
▶︎【EVの回生ブレーキを検証】富士山の五合目から下ると充電量は何kWh増える?
(メリット6)「ゼロ・エミッション」で走れる
従来の車はエンジンを搭載し、ガソリンなどの化石燃料を燃やして走っていました。CO2を排出しながら走ることは避けられません。
一方、EVはエンジンではなくモーターで走ります。化石燃料は使わないので、CO2だけでなく、CO(一酸化炭素)、HC(炭化水素)、NOx(窒素化合物)、PM(粒子状物質)などの大気汚染物質を出さないことから、ゼロ・エミッション・ビークル(ZEV:Zero Emission Vehicle;排出される大気汚染物質〈≒エミッション〉がゼロの乗り物)とも呼ばれます。
走行中のゼロ・エミッションは、EVならではの強みであり、最大のメリットです。EVが普及することによって車の走行による大気汚染を抑えることができるのです。
最もいくら走行中はゼロ・エミッションでも、「車を走らせる電気を火力発電所で作っていたら意味がない」との意見もあります。さらに、EVはバッテリーを製造するときに多くのCO2を発生させるという見方もあります。しかし、現在は太陽光発電など再生可能エネルギーによる発電や製造時の脱炭素化が進んでいます。あらゆる段階でカーボンニュートラルの実現を目指して進んでいるのが、今の世界の潮流です。
〈図〉ガソリン車とEVの違い

(メリット7)各種の補助金・減税が受けられる

走行コストだけではなく、EVは購入コストも低く抑えられます。たしかにガソリン車などに比べると車両価格は高めですが、EVは購入時に国などから補助金を受けられるメリットがあるのです。
国が用意しているのが経済産業省の「CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金)」で、EV購入時の補助金額は2022年度では最大85万円となっています(ただし、4年間保有する義務が発生)。また、自治体がEVなどの環境性能に優れた車種への補助金を用意している場合もあります。
さらに、エコカーとして各種減税もあります。自動車取得税に代わって登場した「環境性能割」は、環境性能に応じて取得価額(≒購入・取得にかかった総額)の最大3%が課されますが、EVは非課税です。また、購入時および初回車検時にかかる重量税は免税(100%減税)、自動車税も、EVは登録翌年度分が概ね75%減税(東京都と愛知県では5年間免税)になります。たとえば、日産「リーフX(40kWh)」をモデルケースに見てみると、83万4500円も優遇を受けられるのです。
〈表〉日産「リーフX(40kWh)」の補助金・減税例1)
| 項目 | 減税額(減税率) | 補助金額 |
|---|---|---|
| 重量税 | 3万円(100%) | |
| 自動車税(登録翌年度) | 1万8500円(75%) | |
| 環境性能割 | 非課税 | |
| CEV補助金 | 78万6000円 | |
|
総額 |
83万4500円 |
|
※メーカー希望小売価格:370万9200円(税込)の場合。2022年10月時点の情報です
EVの場合、自動車税はガソリン車のもっとも安い区分(排気量1000cc未満)と同額の年額2万5000円となるので、減税期間が終わったあとも税負担は少なくて済みます。
なお、基本的に各種の補助金は予算上限に達すると受付終了となります。現在、申請を受け付けているのかどうかなど、詳細情報については以下の記事をご覧ください。
参考資料
1)日産「エコカー減税対象車:日産リーフ」
〈コラム〉EVなら夏場の「富士山マイカー規制」から除外される

富士山では、夏場に登山客や観光客が集中することによる交通渋滞を解消するため、「富士山マイカー規制」が実施されています。ところが、山梨県の富士スバルラインではEVや燃料電池自動車(FCV)は規制の対象外となっていて、マイカーであっても通行OK(2022年度までの実績)なのです。
通行規制は富士山だけではありません。海外では、大気汚染による環境悪化や森林破壊を防ぐため、ガソリン車やディーゼル車の都市部・山間部への乗り入れを禁止する動きもあります。
▼EVをおトクに楽しむポイントサービスはこちら
EVの4つのデメリット
ものごとにはメリットもあればデメリットもあるものです。メリットに比べれば数は少ないものの、EVにもガソリン車と比べて課題となっている点が存在します。実際に利用して感じた4つのデメリットを紹介しましょう。
(デメリット1)車種が少ない

日産「アリア」や「サクラ」、三菱「eKクロスEV」などが発売されて、日本の自動車メーカーから国内向けに発売されているEVの車種も次第に増えてきました。また、韓国のヒョンデが「IONIQ 5」を発売、中国のBYDが来年には日本で3車種のEVリリースを発表するなど、日本のユーザーにとってEVの選択肢は確実に広がってきています。
とはいえ、大容量バッテリーを搭載したEVはまだ高価な高級車がほとんどです。今の段階で、新車価格が300万〜400万円台以下で買える車種と考えると、中古車も含めて選択肢が少ないのが実状です。
(デメリット2)充電に時間がかかる

わざわざガソリンスタンドに行かず、燃料を補充できるのはEVのメリットです。しかし、ガソリン車の給油が数分で終わるのに対し、EVの普通充電は数時間かかります。充電スポットにある急速充電器を利用する場合も30分が基準となっています。
ガソリン車のように「数分もあれば満タン」というわけにいかないのはEV購入を検討する人にはデメリットと感じるでしょう。
EVに乗り慣れたユーザーとしては、普通充電は「寝ている間に満タンにできる」から便利ですし、急速充電はロングドライブの休憩として過ごします。つまり、ガソリン車では当たり前だった「ガソリンタンクがほとんど空になるまで走って給油する」というスタイルから、「バッテリー残量を見ながら走り方や休み方を工夫する」といった、車の使い方の変化を受け入れることが大切になってきます。
充電に時間がかかるということよりも、こうしたライフスタイル変革を求められることが、ガソリン車の常識を基準とした場合のデメリットと言えるのかもしれません。
【あわせて読みたい記事】
▶電気自動車の充電時間はどのくらい? 普通充電・急速充電の目安を解説
(デメリット3)高速道路のSAで「充電渋滞」が起こる

ロングドライブの途中、高速道路SA(サービスエリア)やPA(パーキングエリア)の充電スポットで充電しようと思ったとしましょう。しかし、充電スポットの前には順番待ちのEVの列ができていて、1時間も待たされることに…。これが「充電渋滞」です。このようなことが時折起こることがあります。
これはEVのデメリットというより、最適な充電インフラの整備に関する問題です。SAの多くは、まだ急速充電器を1台しか設置していません。ひとつの充電スポットに複数台の急速充電器を設置したり、あるいは急速充電器をもっと高出力にしたりするなど、充電インフラにはまだ課題もあります。
ただし、充電スポットの数そのものは比較的多くあります。コンビニエンスストアやショッピングモールの駐車場、カーディーラーなど、地域によってはガソリンスタンドよりも多いくらいです。
【あわせて読みたい記事】
▶︎電気自動車もバッテリー上がりを起こす?専門家が教える判断方法や解決策
(デメリット4)EVを上手に活用するには充電の知識が必要
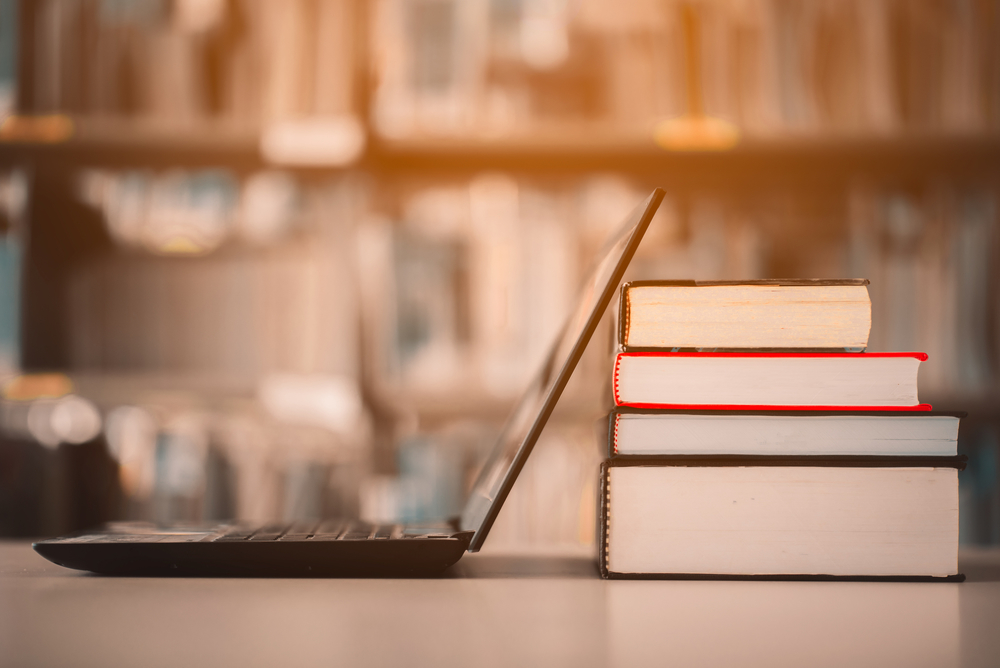
EVを上手に活用するには、電気や充電に関してある程度の知識があると安心です。
たとえば、出力3kWの普通充電器を使い、40kWhバッテリー搭載のEVを「バッテリー残量30%」から「バッテリー残量80%」まで、50%(20kWh)を充電するとします。その場合、頭の中で「20kWh÷3kW=6.67h」と計算し、「約6時間半の充電時間が必要だ」と判断しなければなりません。
〈図〉普通充電の計算式の例

外出先で急速充電器を使うなら別の考え方も必要になります。なぜなら、急速充電器は時間ごとの課金になるからです。また、時間あたりの料金は同じでも、「出力50kWの急速充電器」と「30kWの急速充電器」では充電できる電力量が単純計算で6割も違います。
このように、実際に運用する場合、電気の単位(kWとkWhの違い)、電力の計算方法、充電器の性質などは最低限知っておく必要があります。ほとんどが中学校の理科レベルの知識ではあるものの、苦手意識がある人は苦労する可能性はあります。
「EVのデメリット」だと誤解されている3つのこと

EVにネガティブな印象を抱いている人は少なくありません。車体価格が高い、航続距離が短い、充電スポットが少ない…。このような思い込みから「EVに乗るのはハードルが高い」と考える人が多いようです。しかし、購入費用は補助金や減税措置で抑えられますし、最近のEVは航続距離も短くないのです。
車体価格が高い→補助金などで車体価格を抑えられる
航続距離が最低でも300kmは欲しいと考えると、60kWh以上の大容量バッテリーを搭載したEVを選ぶ必要があります。バッテリーの価格は車体価格の大きなウエイトを占めているので、大容量バッテリー搭載車種は、どうしても高価な印象になってしまいます。
とはいえ、大容量バッテリー搭載車種はそもそもが高級車であることがほとんどです。たとえば、BMWのSUVであるエンジン車の「X3」は約720万円〜であるのに対して、EVモデルの「iX3」は約860万円と、その差はおよそ140万円程度(2022年10月現在)。EVの場合、国のCEV補助金などを活用すれば、税制の優遇もあるので、実質的なユーザー負担額の差はより少なくなると言えます。
EVにはガソリン車と比べてランニングコストが抑えられるメリットもあるので、トータルで考えると一概に「高い買い物」とは言い切れません。
航続距離が短い→航続距離300km以上の車体も少なくない
日産「リーフ」なら40kWhモデルでも航続距離は322km、60kWhモデルなら450kmに達します(WLTCモード※)。片道200km以上も走るような使い方をしなければ、途中で何度も充電しなければならないような不便さはありません。実際にEVに乗ってみれば、日本の平均的なマイカーの使い方の場合、外出先で急速充電をする機会はそれほど多くないことがわかります。
※WLTCとは、「世界統一試験サイクル」といわれる国際的な試験方法に基づいて測定されたデータのこと
【あわせて読みたい記事】
▶︎電気自動車の航続距離の目安は何km? 車種別の航続距離一覧も紹介
充電スポットが少ない→全国に2万1000カ所以上ある
また、公共の場所にある充電スポットも着々と増えており、ガソリンスタンドの6割以上に上る約2万1000カ所以上となっています(2022年3月時点ゼンリン調べ)。この数を少ないと感じる人もいると思いますが、家充電をメインにする人の場合、これらの充電スポットはサブ的な位置づけです。つまり、そもそもガソリンスタンドと同程度の数が必要ではないのです。この問題は、EVの利用方法を知ることで解消されるでしょう。
さらに、よく指摘されるバッテリーの寿命に関しても、日産「リーフ」に「8年16万キロ保証」がついていることからもわかりますが、問題になるほど短命ではありません。
〈表〉「デメリット」だと誤解されることが多いEVの情報一覧
| 誤解されている情報 | 正しい情報 |
|---|---|
| 車体価格が高い | 500万円台以上の車種が多いのは事実だが、現在は実質200万円前後で購入できる軽自動車もリリースされ、各種補助金や減税、維持費用のメリットで、実際には自家用車を所有するためのトータルの費用は抑えられる。 |
| 航続距離が短い | 航続距離300km以上の車種も少なくない。日常的に1日で300km以上走るような車の使い方をする人やケースは多くない。 |
| 充電スポットが少ない | 全国の充電スポット数は2万カ所以上に上り、ガソリンスタンドの約6割。また、家充電する場合は外部の充電スポットの利用頻度自体が低い。 |
現時点でもメリットは多い。今後の進化にも期待しよう
ここまで読んでくださった人は、きっとEVの購入や所有に少しでも興味のある人でしょう。実際に購入を前向きに考えている人かもしれません。もし、ご自宅のガレージに充電器を設置できる環境であれば、「ぜひ一度、所有してみてください!」と背中を押したいと思います。EVがよく指摘される航続距離や充電スポットの問題は、実際に使ってみると「誤解だった」「工夫すれば気にならない」などと気づけることがほとんどです。
最もネックとなるのは、現時点の日本では選べる車種が少ないことでしょう。しかし、これからの時代、車種が増えていくことは間違いありません。自分が本当に欲しいと思えるEVの登場を待つのも選択肢のひとつです。これからますます、EVの進化に注目し、期待してください。